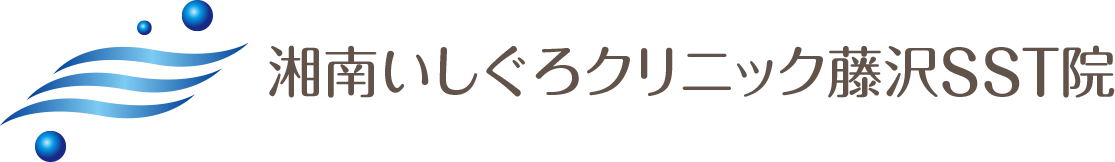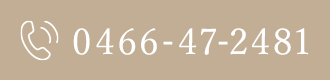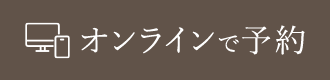胆石症について
 胆嚢は、肝臓と十二指腸を繋ぐ管の途中に存在しており、消化液である胆汁を一時的に蓄える働きを担っている臓器です。
胆嚢は、肝臓と十二指腸を繋ぐ管の途中に存在しており、消化液である胆汁を一時的に蓄える働きを担っている臓器です。
胆汁にはコレステロール、酸、色素、タンパク質、無機質など多様な成分が含まれており、これらの濃度が変化することで結晶化し、石が形成されることがあります。
こうした結石が胆嚢や胆管にできることで引き起こされる病気を「胆石症」と呼びます。
結石ができた場所によって現れる症状は様々で、全く症状が出ない場合もあれば、みぞおち付近に強い痛みが走ったり、吐き気・嘔吐、発熱などを伴ったりすることもあります。
胆石症の原因について
胆石ができる背景には未解明な部分もありますが、脂質の多い食事、乱れた生活リズム、精神的な緊張、細菌による感染などが主な要因とされています。
遺伝的な体質も関与していると考えられていますが、発症の大半は日々の食習慣やライフスタイルに起因しています。
特に近年では、食文化の欧米化により脂肪の摂取量が増加しており、それに伴って胆石症の患者数も増えている傾向があります。
胆石症の症状について
胆石による発作
 脂っこい食事を摂った後などに、右側の肋骨下やみぞおち付近に激しい痛みが現れることがあります。
脂っこい食事を摂った後などに、右側の肋骨下やみぞおち付近に激しい痛みが現れることがあります。
この痛みは、肩の方まで広がることもあります(放散痛)。
発熱・寒気
 胆石が胆嚢や胆管の出口を塞ぐことで胆汁の流れが滞り、胆嚢や胆管に炎症や感染が起こると、腹痛に加えて熱が出たり、寒気を感じたりすることがあります。
胆石が胆嚢や胆管の出口を塞ぐことで胆汁の流れが滞り、胆嚢や胆管に炎症や感染が起こると、腹痛に加えて熱が出たり、寒気を感じたりすることがあります。
黄疸
 黄疸とは、眼球の白い部分や皮膚が黄色く変色する症状です。胆管にできた結石が胆汁の通り道を塞ぐことで、胆汁が十二指腸へ排出されずに血液中へ流れ込むことで起こります(閉塞性黄疸)。
黄疸とは、眼球の白い部分や皮膚が黄色く変色する症状です。胆管にできた結石が胆汁の通り道を塞ぐことで、胆汁が十二指腸へ排出されずに血液中へ流れ込むことで起こります(閉塞性黄疸)。
この状態では、皮膚にかゆみが生じることが多く、また尿の色が濃くなり、紅茶やコーラのような色合いになることもあります。
胆石症の検査について
血液検査
胆嚢や胆管に細菌感染が起こると、白血球の増加など炎症を示す数値が上昇します。また、胆石が胆管に移動して胆管炎を引き起こした場合には、肝機能や胆道系の酵素の値が高くなる傾向があります。
腹部超音波検査・腹部CT検査
胆石の有無、胆嚢の腫れや壁の肥厚、胆汁のうっ滞による胆管の拡張の有無などを確認します。これらの画像検査は、胆石症の診断において非常に有用です。
腹部MRI検査
MRCPという検査では、MRIを用いて胆嚢・胆管・膵管を一度に観察することが可能です。放射線を使わないため、身体への負担が少なく、CTでは見つけにくいタイプの結石を発見できる可能性もあります。
胆石の合併疾患について
胆石に伴って最も頻繁に見られる合併症は「胆嚢炎」で、胆石が引き金となって胆嚢に炎症が生じる状態です。
胆嚢は、総胆管という細い管を通って膵臓の近くを経由し、十二指腸へと繋がっています。胆石がこの経路に落ちて詰まることで、炎症を引き起こすケースも多く見られます。代表的なものに、総胆管結石による「胆管炎」や「急性膵炎」があり、いずれも重篤な感染症です。抗菌薬が普及している現代でも、命に関わることがあるほど深刻な疾患です。
これらの病態では、外科的手術だけでなく、内視鏡による処置や血管内治療が必要になることもあり、症状によっては数カ月に及ぶ入院が必要となる場合もあります。
また、高齢者の場合は「がん」のリスクにも注意が必要です。胆石症の手術を受けた方の中には、手術後にがんが見つかるケースも珍しくありません。慢性的な炎症を繰り返している方では、CTや超音波などの画像検査だけでは正確な診断が難しいこともあるため、特に高齢の方は慎重な経過観察が求められます。
胆石症の治療について
胆石症は、症状の有無やその強さに個人差があるため、治療方針も人それぞれです。胆石が確認されても痛みなどの症状がない場合には、積極的な治療は行わず、食事内容を調整しながら経過を観察します。
一方で、強い痛みがある場合や胆嚢炎を併発している場合には、速やかな対応が求められます。治療法には、薬剤で結石を溶かす「溶解療法」、体外から衝撃波を用いて石を砕く「体外衝撃波結石破砕療法」、内視鏡を使って胆管内の結石を除去する「内視鏡的総胆管結石除去法」、そして胆嚢ごと摘出する「胆嚢摘出術」などがあり、結石の位置や患者様の体調に応じて最適な方法が選ばれます。
※治療が必要と判断された場合には、適切な時期に専門医療機関へのご紹介を行っております。