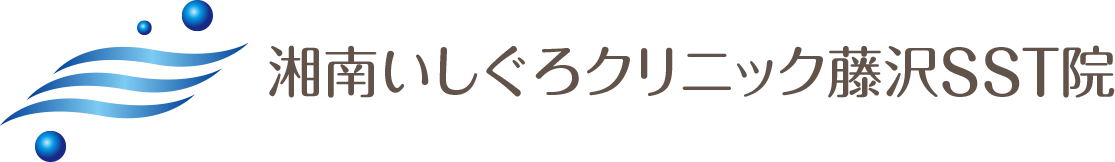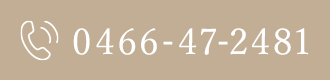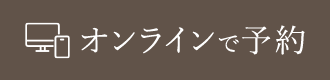長期間の便秘症について
 健康な便の約80%は水分で構成されています。水分量が過剰になると便は柔らかくなり、下痢に至ることがあります。
健康な便の約80%は水分で構成されています。水分量が過剰になると便は柔らかくなり、下痢に至ることがあります。
一方で、水分摂取が不足したり腸で水分が過度に吸収されたりすると、便が硬くなり、排便が困難になることがあります。
また、排便のタイミングを逃す習慣が続くと、便が腸内に溜まっても自然な便意を感じにくくなり、結果として便秘を引き起こすことがあります。食事から排泄までの流れは個人差があるものの、通常はおよそ1日かかります。毎日排便がなくても、排便時に無理なく出せて、残便感がなければ問題はありません。
便秘とは、排便時に強く力まないと出ない、痛みを伴う、あるいは排便後もすっきりしない感覚が残る状態を指します。 主な原因は食物繊維の摂取不足や運動不足ですが、消化器系の疾患が背景にある場合もあります。
病気が関係していない場合でも、便が長時間腸内に留まることで有害物質が発生し、体調に悪影響を及ぼすことがあります。
一時的な体調不良で便秘になることは珍しくありませんが、便秘が長引いたり、下痢と交互に繰り返したりしている場合には、医療機関での診察を受け、適切な治療を受けることが大切です。
便秘症の原因について
 便秘が起こる背景には、排便に関わる働きの低下や、便に含まれる水分量の不足が関係しています。便秘は大きく分けて2つのタイプがあり、腸の病気がないにもかかわらず腸の動きに異常がある「機能性便秘」と、腸そのものに疾患があることで生じる「器質性便秘」があります。
便秘が起こる背景には、排便に関わる働きの低下や、便に含まれる水分量の不足が関係しています。便秘は大きく分けて2つのタイプがあり、腸の病気がないにもかかわらず腸の動きに異常がある「機能性便秘」と、腸そのものに疾患があることで生じる「器質性便秘」があります。
さらに、服用している薬の影響で起こる「薬剤性便秘」、神経系の障害や糖尿病などの内分泌系の病気に伴って現れる「症候性便秘」といった分類もあります。
機能性便秘について
便秘の多くは「機能性便秘」と呼ばれるタイプに該当します。このタイプはさらに3つの種類に分けられ、「弛緩性便秘」「痙攣性便秘」「直腸性便秘」があります。
弛緩性便秘
大腸の動きが鈍くなり、筋肉が緩んでしまうことで、便が腸内に長く留まる状態です。その結果、便の水分が過剰に吸収されてしまい、硬くなって排出が困難になります。
便が腸内に滞留する時間が長くなると、腸内細菌による異常な発酵や腐敗が起こり、有害な物質やガスが発生します。
これにより、腹部の不快感だけでなく、肌荒れや身体機能の低下など、全身に影響が及ぶこともあります。
弛緩性便秘の主な要因としては、水分摂取の不足、食物繊維の不足、運動不足、極端なダイエットなどが挙げられます。
痙攣性便秘
腸の働きは自律神経によって調整されていますが、過度な精神的・身体的負荷がかかると、そのバランスが崩れ、副交感神経の機能に影響が及びます。その結果、腸管が過剰に収縮し、痙攣を起こすことがあります。
このような状態では、排便時に強く力まないと便が出にくくなり、出たとしても量が少なく、硬くて小さな粒状の便になる傾向があります。
排便後もすっきりしない感覚が残り、下腹部に痛みを感じることもあります。 痙攣性便秘は、便秘と下痢を交互に繰り返すタイプの便秘症に多く見られ、過敏性腸症候群(IBS)のうち、便秘型や混合型の症状としても知られています。
直腸性便秘
食べた物は結腸を通ってゆっくりと移動し、直腸に一時的に蓄えられます。便が一定量に達すると、直腸の神経が刺激されて自然な排便の感覚が生じます。
しかし、忙しさなどで排便のタイミングを逃し続けると、直腸に便が溜まっても便意を感じにくくなり、肛門の筋肉がスムーズに緩まなくなります。このような状態が「直腸性便秘」と呼ばれます。便が過剰に蓄積されると、排出が困難になってしまいます。 高齢者に多く見られる傾向がありますが、痔による痛みで排便を避ける習慣がついてしまうことも、直腸性便秘の原因となることがあります。
器質性便秘について
大腸ポリープや大腸がんの進行による腸管の狭窄、クローン病、あるいは腹部の手術後に起こる癒着などによる腸閉塞などによって起こる便秘です。
普段は排便に問題がない方が突然便秘になり、それが長引くような場合や、血が混じった便、強い腹痛、吐き気、嘔吐などの症状が伴う場合には、速やかな医療的対応が必要です。
また、器質性便秘の状態で、ドラッグストアで販売されている下剤や便秘薬などを使って無理に排便しようとすると、かえって症状が悪化する危険性があります。原因を正確に見極めたうえで、適切な治療を受けることが重要です。
便秘症を起こす疾患について
便秘を引き起こす疾患は多岐にわたります。腸そのものに異常がある「器質性便秘」では、大腸憩室症、大腸ポリープ、大腸がん、腸閉塞、潰瘍性大腸炎、クローン病などが原因となり、便の通過が妨げられることで症状が現れます。
一方、大腸以外の臓器やホルモン・神経系の異常によって起こる「症候性便秘」では、甲状腺機能低下症による代謝の乱れ、摂食障害やうつ病などの精神疾患、糖尿病による神経障害、神経損傷などが関係しています。
女性の場合は、子宮筋腫が影響することもあります。 また、便秘と痔は密接な関係があり、硬くなった便を排出する際に肛門が傷ついたり、痔の痛みから排便を避ける習慣がついたりしてしまうことで、直腸性便秘を引き起こすこともあります。これらは互いに悪循環を生むことがあります。
こうした疾患が原因となっている便秘は、放置すると症状が進行する恐れがあるため、早めに検査を受けて原因を特定し、適切な治療を受けることが望ましいです。
便秘症の検査・診断について
まずは問診にて、便秘の症状や始まった時期、排便の頻度や状態に加え、これまでの病歴や服用中の薬、体調の変化、その他の関連症状などについて詳しく伺います。
排便に関する話題は抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、正確な情報を共有いただくことで、原因の特定がよりスムーズに進められます。 問診後には、腹部の状態を確認するための触診や聴診を実施します。
加えて、必要な方には腹部のレントゲン撮影、超音波検査、血液検査なども追加します。大腸カメラ検査が必要と判断された場合は、専門の医療機関へのご紹介も可能です。
腹部のCT・MRI検査
茅ヶ崎の本院では、状況に応じて当日中に腹部CT検査やMRI検査を受けていただくことが可能です。
便秘症の治療について
機能性便秘の場合は、日常生活の改善と薬物療法を組み合わせて進めます。一方、症候性便秘や器質性便秘では、まず原因となる疾患の治療が優先されます。 薬の影響による便秘(薬剤性便秘)の場合は、処方内容の見直しなどを提案します。
薬物療法
 便秘に対する薬は多岐にわたり、特に下剤だけでも種類が豊富です。便秘のタイプや生活習慣を考慮しながら、最も適した薬を選定しています。
便秘に対する薬は多岐にわたり、特に下剤だけでも種類が豊富です。便秘のタイプや生活習慣を考慮しながら、最も適した薬を選定しています。
再診時には、薬の効果を確認しながら、必要に応じて処方の変更や用量の調整を行い、きめ細かな対応を心がけています。
生活習慣の改善
 不規則な生活リズムや偏った食事、無理なダイエットなどは便秘の原因となります。
不規則な生活リズムや偏った食事、無理なダイエットなどは便秘の原因となります。
水分を意識して摂ること、野菜をこまめに取り入れること、そして適度な運動を継続することが、排便の安定には欠かせません。気になることがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。