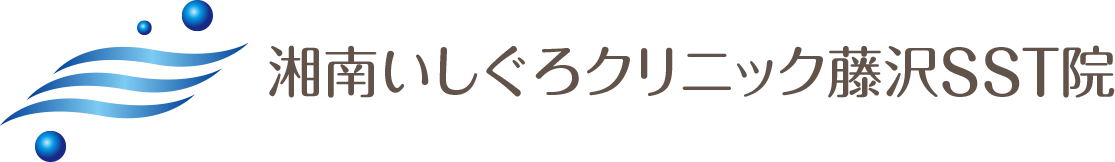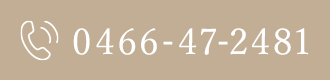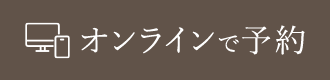糖尿病(血糖値が高いままの状態)について
 糖尿病は、インスリンという物質の分泌が足りなくなる「インスリン分泌不全」と、インスリンそのものの機能が低下する「インスリン抵抗性」が要因とされている疾患です。これらの影響で、血液中の血糖(ブドウ糖)が増え続けてしまうのです。
糖尿病は、インスリンという物質の分泌が足りなくなる「インスリン分泌不全」と、インスリンそのものの機能が低下する「インスリン抵抗性」が要因とされている疾患です。これらの影響で、血液中の血糖(ブドウ糖)が増え続けてしまうのです。
糖尿病の原因について
1型糖尿病の場合について
膵臓でインスリンを分泌するβ細胞が損傷し、インスリンの分泌が減少することで発症します。
病気の発症原因は特定されていませんが、ウイルス感染や遺伝要因などが免疫系に異常を引き起こし、自己免疫が体内で起こった結果、自身の抗体が体を攻撃することで起こるのではないかと考えられています。
自己抗体には抗GAD抗体や抗IA-2抗体などがあり、これらが膵臓を攻撃しβ細胞を破壊するとされています。
1型糖尿病のタイプ
1型の場合、症状が進行すると、インスリンがほとんど生産できなくなります。そのため、治療ではインスリンの注射が行われます(インスリン依存状態)。
1型糖尿病は、インスリン依存状態が進むスピードに応じて「劇症」「急性発症」「緩徐進行」に大別されます。
劇症
最も進行が速いタイプになります。短期間でインスリンが分泌されなくなるため、直ちにインスリン治療を始めないと、命を落としてしまう恐れがあります。
このタイプでは、血糖値がかなり高くなることがよくある一方で、急な症状の出現により、HbA1cを1~2カ月分測定した平均でも、それほど高くない傾向が見られます。また、自己抗体の存在があまり確認できないのも、急性1型糖尿病の特徴です。
急性発症
急性発症型は、1型糖尿病患者の中で一番多いタイプです。発症後から数カ月でインスリン依存状態に陥る傾向があります。治療の開始により、短期間で膵臓の機能が向上し、「ハネムーン期(インスリン治療が不要になる期間)」に入ることもあります。この期間が数カ月継続した後、再びインスリン治療が必要な状態に戻ってしまう可能性もあります。また、血液検査にて、自己抗体が検出される患者様も少なくありません。
緩徐進行(かんじょしんこう)
インスリンの量が年単位で徐々に減っていくタイプです。初期段階では、2型糖尿病と同様に、血糖値をコントロールするためにインスリン注射をする必要はありません。
ただし、自己抗体検査で陽性となったことで、このタイプだと判明できた方もいらっしゃいます。
このタイプは、インスリンを少しだけ分泌するものの、膵臓に負担をかける薬の服用は好ましくないとされています。そのため、膵臓への負担が少ない薬や早期インスリン治療が勧められます。
2型糖尿病の原因について
日本国内にいる糖尿病の患者様の95%以上が2型糖尿病に該当します。
インスリンの減少や、機能低下による「インスリン抵抗性」によって発症します。これらは主に、以下の要因が引き金となって起こるとされています。
- 食べすぎ、飲みすぎ、早食い
- 運動不足
- 高脂肪食
- 肥満
- ストレス
- 不規則な食生活
- 遺伝
- 年齢(40歳以上から2型糖尿病にかかりやすくなる)
妊娠糖尿病が起こる原因について
妊娠すると母体からエネルギーが届けられます。それにより、お腹の赤ちゃんは大きくなるのです。通常、胎盤からインスリンの働きを抑える物質が分泌されるため、お母さんの血糖値はあまり低下しません。そのため、妊娠中は妊娠していない時よりも、血糖値が高くなりやすいのです。
妊娠糖尿病は、妊娠前まで糖尿病と診断されてこなかった方で、糖尿病には当てはまらない糖代謝異常が見られる状態です。妊娠する前に糖尿病と診断されていた場合は、「糖尿病合併妊娠」とされます。
妊娠糖尿病は、赤ちゃんを出産した後、血糖値が基準値に落ち着く傾向にあります。ただし、今後糖尿病を発症するリスクも高いと指摘されており、定期的に検査を受けて健康状態をチェックすることが大切です。さらに、出産した後でも、糖代謝異常がないか引き続きチェックしていく必要があります。妊娠糖尿病は主に、以下の要因によって起こります。
- 遺伝
- 肥満
- 高齢妊娠(35歳以上での出産)
その他の原因によって起こる糖尿病について
その他の原因による糖尿病では、次の要因が考えられます。治療方法や症状は通常の糖尿病と同様に実施します。
- 遺伝子異常
- 肝臓や膵臓の疾患があり、手術を受けた経験がある
- 内分泌疾患(血糖値を上昇させるホルモンが多く分泌される)
- ステロイド薬を使用する治療を受けている
糖尿病は「生活習慣や食習慣の乱れによって発症する」と言われており、「贅沢病」と呼ばれることもありました。しかし、遺伝や薬剤、他の疾患が原因で発症するケースも存在します。
血糖値が高いまま治療を受けずに過ごしていると、合併症が進行し、命に危険が及ぶリスクが高くなるため、放置は禁物です。
糖尿病の初期症状・症状について
1型糖尿病の症状について
1型糖尿病は急性合併症と呼ばれ、症状が突然現れるのが特徴です。典型的な症状は以下の通りで、重症化すると嘔吐、吐き気、呼吸困難、または意識を失うリスクもあるため、要注意です。
- 疲れやすくなった
- 頻尿
- 異常に喉が渇く
- 体重が急激に減少する
2型糖尿病の症状について
初期の2型糖尿病では、顕著な症状はほとんど現れません。しかし、「糖尿病合併症」が進行すると、以下の症状が現れる恐れがあります。
- 目がかすむ
- 皮膚の乾燥、かゆみ
- 疲れやすくなる
- 喉が渇きやすくなる、お腹が空きやすい
- 手足の感覚が鈍くなる、チクチクとした痛みがある
- 頻尿
- 感染症が頻繁に起こる
- 性機能の問題(ED)
- 皮膚の傷(切り傷など)がなかなか治癒しない
妊娠糖尿病による影響・リスクについて
母体に症状が現れることは稀です。しかし、血糖値が高いままですと、妊娠中や出産時、産後に以下のような影響が出る恐れがあります。
赤ちゃんへの影響
血糖値が上昇すると、母体内の血液中に糖分が過剰になり、赤ちゃんへ届く栄養が過剰になる恐れがあります。それにより、赤ちゃんが子宮内で過度に成長してしまい、出産時に産道を通過できなくなり、負傷するリスクが高くなります。
出産後の赤ちゃんへの影響
お母さんの血糖値が高いと、乳児の体内で、血糖を下げる機能が盛んに働いてしまう恐れがあります。この状態で出産すると、これまで受け取っていた栄養が供給されなくなり、血糖値が著しく低下する危険性があります。さらに、黄疸(皮膚などが黄色くなる)の出現、血液量が増加する疾患の発症、呼吸困難により仮死状態で誕生するといったリスクも高くなります。
母体への影響
妊娠中に高血圧になる、胎児が予定日より早く生まれるといったトラブルのリスクが高くなります。また、出産時に合併症が生じて、帝王切開に至るケースもございます。
糖尿病の検査と診断方法について
血液検査について
糖尿病の検査や診断時に、通常行われる血液検査の詳細についてご説明します。
血糖値
血中のブドウ糖濃度を測定し、食事前・後(食事の二時間前・後)それぞれの変動を確認します。その結果から、インスリンの効果が適切かどうかを判断することができます。
具体的な基準値は以下の通りです。
空腹時血糖の数値
| 正常 | 100mg/dl未満 |
|---|---|
| 正常高値血糖 | 100-109mg/dl |
| 予備軍型 | 110-125mg/dl |
| 糖尿病型 | 126mg/dl以上 |
食後血糖の数値
| 正常 | 140mg/dl未満 |
|---|---|
| 予備軍型 | 140-199mg/dl |
| 糖尿病型 | 200mg/dl以上 |
HbA1c
直近約1~2カ月分の血糖値を示す数値です。健康診断の前日に生活習慣を整えて血糖値を下げても、HbA1cには影響しません。HbA1cの基準値は次の通りです。
| 正常 | 5.6% 未満 |
|---|---|
| 予備軍型 | 5.6-6.4% |
| 糖尿病型 | 6.5%以上 |
上記検査に加えて、血中に存在するインスリンやC-ペプチドを調べる血液検査も存在します。こちらの検査を通じて、血糖を調整するインスリンが適切に分泌されているかを確認することも可能です。インスリンの分泌や作用は、治療方針を立てる際にも非常に重要となります。
糖尿病の尿検査について
以下の数値は、糖尿病の尿検査で明らかになります。
尿中のアルブミン
糖尿病によって合併症を発症すると、腎機能に障害をもたらすリスクを伴います。尿中のアルブミンは、その合併症を早期に発見するのに役立つ検査です。尿中のアルブミンが検出されると、将来、人工透析を余儀なくされる恐れがあるため、早いうちから検査を受けることを推奨します。
以下は、尿中のアルブミンの基準値です。
| 正常 | 30 mg/gCr未満 |
|---|---|
| 早期腎症 | 30-299 mg/gCr |
| 顕性腎症 | 300 mg/gCr%以上 |
糖尿病は自力で治せるのか?治療方法について
糖尿病の患者様の多くは、自力で糖尿病の治療を進めることで、改善できるのを望んでいるかと思います。しかし、糖尿病は自力では完治することができないため、医療機関へ受診する必要があります。これが現状であると聞いた時、多くの方々はショックを受けてしまうかもしれません。
ただし、糖尿病と上手に付き合っていけば、疾病の影響を受けることなく、日常生活を過ごすことは可能です。
糖尿病について学びながら、生活習慣や食生活、適度な運動を習慣として取り入れ、基準値を守るための血糖コントロールが不可欠です。
基準値を維持するために、食事療法、薬物療法、運動療法の3つを中心に取り組み、糖尿病の改善に取り組んでいきましょう。
食事療法で気を付けること
 人間の身体は、摂取した食べ物によって栄養を得ることで、活動することができます。食物から摂取された糖質は吸収され、血液中のブドウ糖に変換され、その濃度が血糖値として現れます。ブドウ糖が過剰になるのを防ぐのは、インスリンというホルモンの役割であり、このインスリンの働きが低下すると糖尿病が発症します。
人間の身体は、摂取した食べ物によって栄養を得ることで、活動することができます。食物から摂取された糖質は吸収され、血液中のブドウ糖に変換され、その濃度が血糖値として現れます。ブドウ糖が過剰になるのを防ぐのは、インスリンというホルモンの役割であり、このインスリンの働きが低下すると糖尿病が発症します。
食事療法では、インスリンの状態に応じて食事内容を改善していきます。食べてはいけないものはありません。しかし、体に必要な栄養素を積極的に摂取し、食生活やカロリーを調整することが重要ですので、これらを守っていただければと思っています。
必要なカロリー摂取量は患者様によって異なります。適正なエネルギー摂取量から適切なカロリーを算出し、1日の食事に取り入れて、栄養バランスの整った食事内容を続けましょう。
コツ
日々の食事を少し改善するだけでも、治療効果が実感しやすくなります。食べすぎ・飲みすぎ・早食いは避けながら、「腹八分目」を心がけましょう。また近年では、以下のような食べ方が血糖管理に有効だと評価されています。実際に試す方も増えています。
- 最初に野菜を摂ります。これで吸収される糖分を抑えられます。
- お味噌汁やスープなどの汁物を飲んでみましょう。これでお腹を満たし、食べ過ぎを防ぐことができます。
- 肉や魚などの主菜を食べ、身体に必要なタンパク質を補給します。
- ご飯を食べます。炭水化物を最後に摂ることで、急激な血糖値上昇を予防できる効果が期待できるのです。
運動療法で気を付けること
 糖尿病は、「1型糖尿病」と「2型糖尿病」に区分されます。「1型糖尿病」の要因は主に遺伝的要素と言われており、子供や若い世代での発症が多いです。
糖尿病は、「1型糖尿病」と「2型糖尿病」に区分されます。「1型糖尿病」の要因は主に遺伝的要素と言われており、子供や若い世代での発症が多いです。
「2型糖尿病」の原因は、運動不足や食べ過ぎ、肥満といった生活習慣と関連しており、日本では2型糖尿病患者が最も多いとされています。
2型糖尿病の患者様は、生活習慣の改善が必須です。そのため、運動療法を通じて体内で血糖の代謝を高め、血糖値の上昇を防ぐのを目指しましょう。運動を定着させ、筋肉をつけて糖の代謝を促進し、脂肪を減らすことで、インスリンの機能増進に繋がります。
コツ
脂肪燃焼に有効なのは有酸素運動です。ご自分の好きなスポーツや得意なスポーツ、毎日続けられるウォーキングでも、脂肪の燃焼に繋がりますので、治療のために通常行わないような運動をする必要はありません。 少しハードなトレーニングを続けることが大切です。
また、筋トレをして筋肉量を増やすと、脂肪の燃焼効果がさらに得られます。 テレビで紹介されたトレーニングや特別な器具がなくてもできる自重トレーニング、深呼吸でインナーマッスルを鍛えるなど、気軽にできるトレーニングをコツコツ続けましょう。
食事から1時間~1時間半後には血糖値がピークに達しますので、そのタイミングで運動すると良いでしょう。
ただし、糖尿病の方は低血糖にならないように注意しなければなりません。また、運動療法の効果を最大限に得るためには、激しい運動よりも軽い運動を週に3回以上行う方が効果的とされています。
運動療法と食事療法を同時に行うことで、治療効果を得ることができます。 一方だけに力を入れるのではなく、両方を丁寧に取り組んでいきましょう。
薬物療法で気を付けること
 薬物療法は、食事療法や運動療法だけでは効果が得られない方に推奨されます。経口血糖降下薬やインスリン注射を用いて治療を行います。
薬物療法は、食事療法や運動療法だけでは効果が得られない方に推奨されます。経口血糖降下薬やインスリン注射を用いて治療を行います。
患者様の年齢、体型、肝臓と腎臓の機能、合併症の進行具合、インスリン抵抗性やインスリン分泌能の程度に応じて、適切なお薬を選択します。
糖尿病において複数の薬を服用する際、服用する時間や量が異なるお薬があると、覚えるのが難しく、うっかり服用を忘れることもあります。このような場合、決められた服用時間以外に自己判断で服用したり、服用量を変更したりしないよう、ご注意ください。
糖尿病の治療は、主に食事療法や運動療法を重視し、薬物療法は効果が現れない場合にのみ行います。薬物療法が必要な場合でも、食事療法や運動療法を継続することで、お薬の効果を最大限に引き出すことができます。