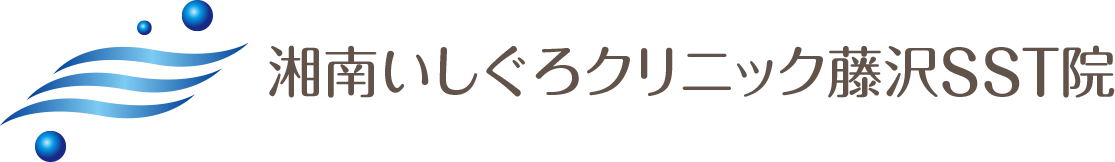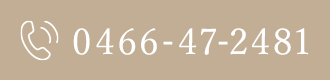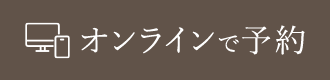脂肪肝について
脂肪肝とは、肝臓に過剰な中性脂肪が蓄積された状態を指します。
主に2つのタイプに分類されており、1つは過度な飲酒によって引き起こされる「アルコール性脂肪肝」、もう1つは飲酒習慣がないにもかかわらず発症する「非アルコール性脂肪肝」です。
エタノール60g相当の飲酒量について
1日あたりのアルコール摂取量がエタノール換算で60gを超える場合、「常習飲酒家」とみなされます。具体的な目安として、以下のような酒量が該当します。
| ビール(アルコール度数5%) | 約1500ml |
|---|---|
| 日本酒(15%)h | 約3合(540ml) |
| 焼酎(25%) | 約1/8合(330ml) |
| ワイン(14%) | 約540ml(3/4本程度) |
| ウイスキー(43%) | ダブルサイズで3杯(180ml) |
脂肪肝のタイプと診断について
- アルコール性脂肪肝
- 非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)
- NAFL: non-alcoholic fatty liver
- NASH: non-alcoholic steatohepatitis
アルコールを摂取していないにもかかわらず発症する「非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)」は、以下の2タイプに分けられます。
脂肪が肝臓に蓄積されるだけの「NAFL(ナッフル)」と、脂肪の蓄積に加えて炎症や線維化が進行する「NASH(ナッシュ)」です。
NAFLは進行性が低く、比較的安定した状態が保たれます。一方、NASHは病状が進むと肝硬変や肝がんを引き起こす可能性があり、近年ではNASH由来の肝がんが増加傾向にあります。
現在、NASHの診断には「肝生検」が用いられています。
これは肝臓に針を刺して組織を採取し、顕微鏡で詳細に観察する方法で、身体への負担が大きく、入院が必要です。
また、肝生検以外にも以下のような検査方法があります。
- FIB-4 indexやNFS(NAFLD fibrosis score)などの簡易評価指標
- 超音波による画像診断
- MRIなどの精密検査
肝脂肪が確認された場合、他の肝疾患が隠れている可能性もあるため、気になる方はぜひ当院へご相談ください。
脂肪肝の原因について
 脂肪肝の主な要因として挙げられるのは、食べすぎやアルコールの多量摂取です。
脂肪肝の主な要因として挙げられるのは、食べすぎやアルコールの多量摂取です。
さらに、肥満体型や糖尿病、ステロイド薬の使用による代謝異常などが引き金となることもあります。
近年では、肥満や生活習慣病を抱える方が増加していることから、脂肪肝の罹患者も増えているのが現状です。
また、非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)は、生活習慣に起因するケースが多いとされていますが、遺伝的な背景が関与している可能性も指摘されています。
PNPLA3やTM6SFといった遺伝子の多型が発症に関係しているという研究も進められていますが、現時点ではまだ検証段階にあります。
脂肪肝の検査について
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、異常があっても自覚症状が現れにくい臓器です。
そのため、脂肪肝になっていてもご本人が気付かないケースも少なくありません。血液検査でALT(GPT)、AST(GOT)、rGPTなどの数値に異常が見つかった場合は、より詳しい検査が必要になります。
血液検査では、ウイルス性肝炎など他の肝疾患の有無を確認するほか、腹部の超音波検査によって肝臓への脂肪の蓄積や腫瘤の有無を調べることができます。
脂肪肝の治療について
 まず、アルコールの摂取が関係しているかどうかを確認し、「アルコール性脂肪肝」か「非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)」のどちらに該当するかを判断します。NAFLDと診断された場合は、「NAFL」か「NASH」かを見極めていきます。
まず、アルコールの摂取が関係しているかどうかを確認し、「アルコール性脂肪肝」か「非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)」のどちらに該当するかを判断します。NAFLDと診断された場合は、「NAFL」か「NASH」かを見極めていきます。
アルコール性脂肪肝の方には、飲酒量を減らす習慣を身につけていただきます。NAFLDで肥満がある方には、食生活の改善と無理のない運動を取り入れていただくことが基本となります。
なお、NAFLDやNASHに対する薬物治療は、現時点では保険適用外の自由診療となっています。
そのため、まずは日々の生活習慣を整え、肝機能を安定させることが治療の中心となります。加えて、定期的な血液検査や腹部エコーなどを通じて、経過を丁寧に追っていくことが大切です。