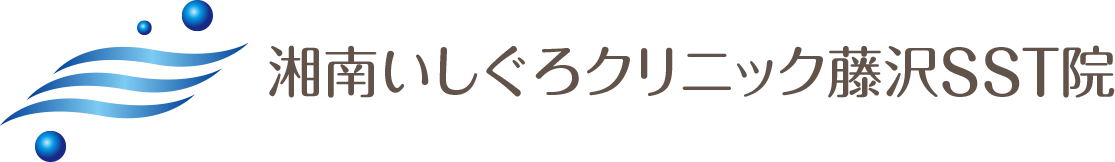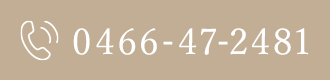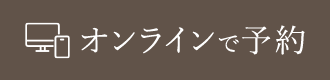以下の症状が現れたら「胃腸炎」発症の合図
- お腹の調子が悪く、熱が出ている
- 突然吐き気や嘔吐が起こる(下痢を伴わない場合もある)
- 水のような便や軟らかい便が何度も出る
- 排便がなくても、お腹が鳴ったり痛みを感じたりする
- 下痢や軟便に血が混じる(血便が出る)
- 何度も便意を感じるのに、少量しか出ない(しぶり腹)
- お腹が痛い、張っている、または不快に感じる
- 胃がムカムカする
- 食欲がなくなり、食事に関心が薄れる
上記の症状に該当される方は、我慢せず、お近くの消化器内科を受診しましょう。
湘南いしぐろクリニック藤沢SST院では、消化器内科専門医が常駐して診療しておりますので、胃腸炎の症状や重症度によって適切な治療や、緊急性に応じた高次医療機関への紹介が可能です。
胃腸炎とは
 胃や腸に炎症が起こるさまざまな病気の総称です。主な症状としては、嘔吐(おうと)、下痢、腹痛、吐き気、食欲の低下などがみられます。
胃や腸に炎症が起こるさまざまな病気の総称です。主な症状としては、嘔吐(おうと)、下痢、腹痛、吐き気、食欲の低下などがみられます。
原因には、感染(いわゆる流行性の「嘔吐下痢症」や「食中毒」)、ストレスによるもの(過敏性腸症候群など)、アレルギーや免疫反応(炎症性腸疾患などを含む)があります。
これらの症状がある場合は、できるだけ早めに消化器内科の専門医を受診することをおすすめします。
感染性胃腸炎(ウイルス性・細菌性)の場合、知らないうちに周囲の人へ感染を広げてしまうおそれがあり、出勤や登校・登園の際には注意が必要です。
また、一般内科を受診した際に感染性胃腸炎と誤って診断され、実際には潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患であったというケースも少なくありません。したがって、安易な自己判断や自己治療は避け、専門的な診察を受けることが大切です。
胃腸炎・食中毒・嘔吐下痢症の違い
「胃腸炎(いちょうえん)」とは、原因の種類にかかわらず、胃や腸に炎症を起こすさまざまな病気の総称です。
これらは原因によっていくつかのカテゴリーや疾患に分類されます。 一方で、「食中毒(しょくちゅうどく)」は、細菌・ウイルス・寄生虫などの病原体を含む食べ物や水を摂取することで、体内に病原体が入り込み、その病原体がつくる毒素が体に作用して発症する病気です。広い意味では、感染性胃腸炎の一種にあたります。
代表的なものには、鶏肉によるカンピロバクター腸炎、卵によるサルモネラ菌感染、辛子レンコンが原因となったボツリヌス菌中毒(重症化すると命に関わることもあります)などがあります。
また、一般的に「嘔吐下痢症(おうとげりしょう)」と呼ばれるものは、多くの場合ウイルス性の感染性胃腸炎です。特定の食事や飲み水が原因というよりは、風邪(急性上気道炎)と同じように、いつどこで感染したのかわからない形で発症することが多いのが特徴です。感染者が触れた物に触れ、それを介して口にウイルスが入ることで感染するため、うがい・手洗いが効果的な予防法とされています。
特に冬場や夏場に流行するロタウイルス(白っぽい下痢)やノロウイルスがよく知られています。
いずれの疾患も、主な症状は嘔吐・下痢・腹痛・発熱・悪寒などで共通していますが、原因や感染経路が異なります。また、病原体や毒素の種類によって症状の出方や重症度にも違いがあります。
胃腸炎の原因
下記は胃腸炎の症状です。
感染
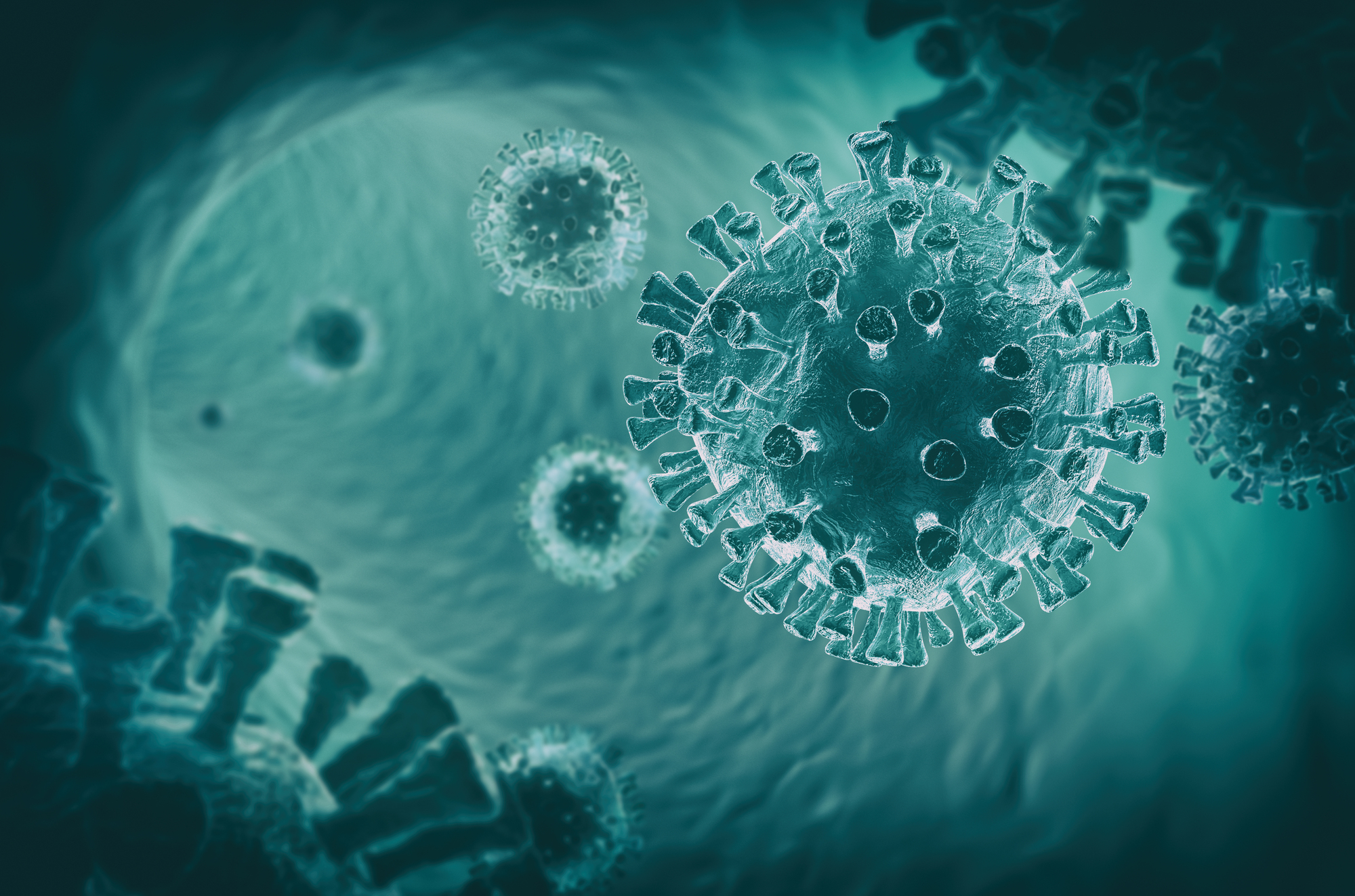 ノロウイルスやロタウイルス、大腸菌やサルモネラ、ビブリオ、寄生虫(赤痢アメーバやジアルジア、クラミジア)などによる感染が主な原因です。
ノロウイルスやロタウイルス、大腸菌やサルモネラ、ビブリオ、寄生虫(赤痢アメーバやジアルジア、クラミジア)などによる感染が主な原因です。
食中毒
 間違った調理方法や保存方法により細菌が繁殖し、食中毒を発症する場合があります。
間違った調理方法や保存方法により細菌が繁殖し、食中毒を発症する場合があります。
水や飲料の汚染
 汚染された水や飲料水の摂取で胃腸炎を発症することがあります。
汚染された水や飲料水の摂取で胃腸炎を発症することがあります。
ストレス
 長きにわたる精神的なストレスが胃や腸に影響を与え、胃腸炎を引き起こす事があります。
長きにわたる精神的なストレスが胃や腸に影響を与え、胃腸炎を引き起こす事があります。
アレルギー反応
 アレルギーのある食品が体内に入る事で、胃腸に炎症が現れます。
アレルギーのある食品が体内に入る事で、胃腸に炎症が現れます。
自己免疫反応
発症原因不明の特殊型腸炎(潰瘍性大腸炎、クローン病、腸管ベーチェットなど)は、自分の免疫が自身の胃腸を攻撃する事で発症します。
胃腸炎症状があればすぐに受診を
最も一般的なウイルス性胃腸炎の場合、通常は風邪(急性上気道炎)と同じように、治療を行わなくても自然に回復することがあります。
しかし、適切な治療を受けないまま放置すると、症状が長引いたり、あるいは本来の診断が誤っており、実際には特殊型腸炎(例:炎症性腸疾患など)が隠れていた場合には、症状が慢性化したり重症化するおそれがあります。
このような事態を防ぐためにも、消化器内科の専門医がいる医療機関を早めに受診することをおすすめします。
脱水症状・電解質異常
嘔吐や下痢によって体内の水分が失われると、脱水症状を起こすおそれがあります。
さらに、下痢によってカリウム(K⁺)が体外へ排出されるため、体内の水分や電解質のバランスが崩れ、疲労感・めまい・頭痛・倦怠感・筋力の低下・だるさなどの症状が現れることがあります。
栄養失調
胃腸炎の症状が長引くと、食欲の低下や食事制限の継続により、栄養不足(栄養失調)を起こすおそれがあります。
栄養失調になると、体力や免疫力が低下し、回復が遅れる原因となるだけでなく、別の病気(二次感染など)を発症する可能性もあります。
胃潰瘍や胃腸出血
胃腸炎による炎症や胃酸の過剰な分泌によって、胃の粘膜が傷つくことがあります。
その結果、胃潰瘍や胃腸出血を起こすリスクが高まる可能性があります。 重症の場合には、胃や十二指腸の壁に穴(穿孔)があくことがあり、その際には緊急で外科手術が必要になることもあります。
感染の拡大
胃腸炎の原因となるウイルスや細菌は感染力が非常に強く、家族や周囲の人に感染を広げてしまう可能性があります。
症状がすっかり治まった後でも、48時間(約2日間)程度は他人にうつすリスクが残っています。
そのため、医療関係の職種や飲食・調理に関わる仕事をされている方は、この期間中の出勤を控えることをおすすめします。
免疫低下
胃腸炎が長期間続く、または症状を繰り返す場合、免疫機能の低下を招くことがあります。
免疫力が低下すると、他の感染症やさまざまな健康トラブルに対する抵抗力が弱まり、他の病気にかかりやすくなる可能性があります。
このようなリスクや合併症を防ぐためには、正確で早期の診断と適切な治療が大切です。
胃腸炎の治療と予防
1問診
 問診で症状が胃腸炎に当てはまるか確認します。
問診で症状が胃腸炎に当てはまるか確認します。
2診察・検査
 腹部を触診して圧痛の程度や範囲を確認した後、腹痛や下痢が強い場合は、腸の腫れや炎症の範囲を正確に把握するために、腹部エコー(超音波検査)や採血を行います。
腹部を触診して圧痛の程度や範囲を確認した後、腹痛や下痢が強い場合は、腸の腫れや炎症の範囲を正確に把握するために、腹部エコー(超音波検査)や採血を行います。
さらに、胃の痛みが強い場合には胃カメラ検査を、血便がある場合には大腸カメラ検査を検討します。
また、若い女性で吐き気だけが症状の場合は、妊娠による「つわり」の可能性を確認するために妊娠検査を行うこともあります。
3診断
 採血データやエコー・に基づいた診断を心掛けております。
採血データやエコー・に基づいた診断を心掛けております。
詳細な検査が必要と判断した場合は、内視鏡検査に対応可能な本院へご案内いたします。
4治療
主に下記の方法で治療を行います。 症状によっては治療法を組み合わせて行う場合があります。
自己管理
胃腸炎の症状が軽い場合は、十分な休養と水分補給が大切です。
このとき、水やお茶だけでなく、電解質を含むスポーツドリンクや経口補水液(OS-1など)を摂ることが推奨されます。
また、腹痛・嘔吐・下痢を和らげるためには、脂っこい食べ物や辛いものなどの刺激物、アルコールは避け、消化の良い食事(おかゆ・うどん・バナナ・ゼリー飲料など)を少量ずつ摂るようにしましょう。
薬物療法
医師の指示に従い、二次感染を防ぐための抗生物質や、症状を和らげる胃腸薬、解熱剤の内服などで治療を行います。
また、脱水症状が強い場合には点滴を行い、症状に応じて鎮痛剤や吐き気止めの注射が使用されることもあります。
感染予防
手洗い・うがいや、食品の十分な加熱、清潔な水の摂取など、基本的な衛生対策を徹底して感染予防に努めましょう。
また、感染が疑われる場合は、他人との接触を避け、消化器内科の専門医に相談することが大切です。
正しい食事管理
胃腸炎の回復期には、消化の良い食品(白米、トースト、鶏肉など)を少しずつ摂ることが推奨されます。
また、食事の間隔や量を適切に保つことも大切です。
胃腸炎は身近でよく見られる病気ですが、放置すると症状が重くなることや、周囲の人に感染させてしまう可能性があります。
自己判断や自己治療は避け、早めに消化器内科などの専門医に相談することが重要です。