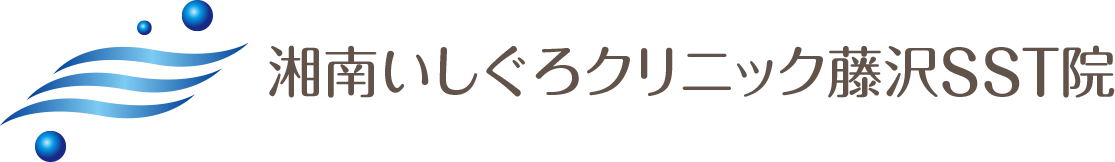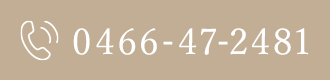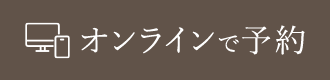当院の消化器内科について
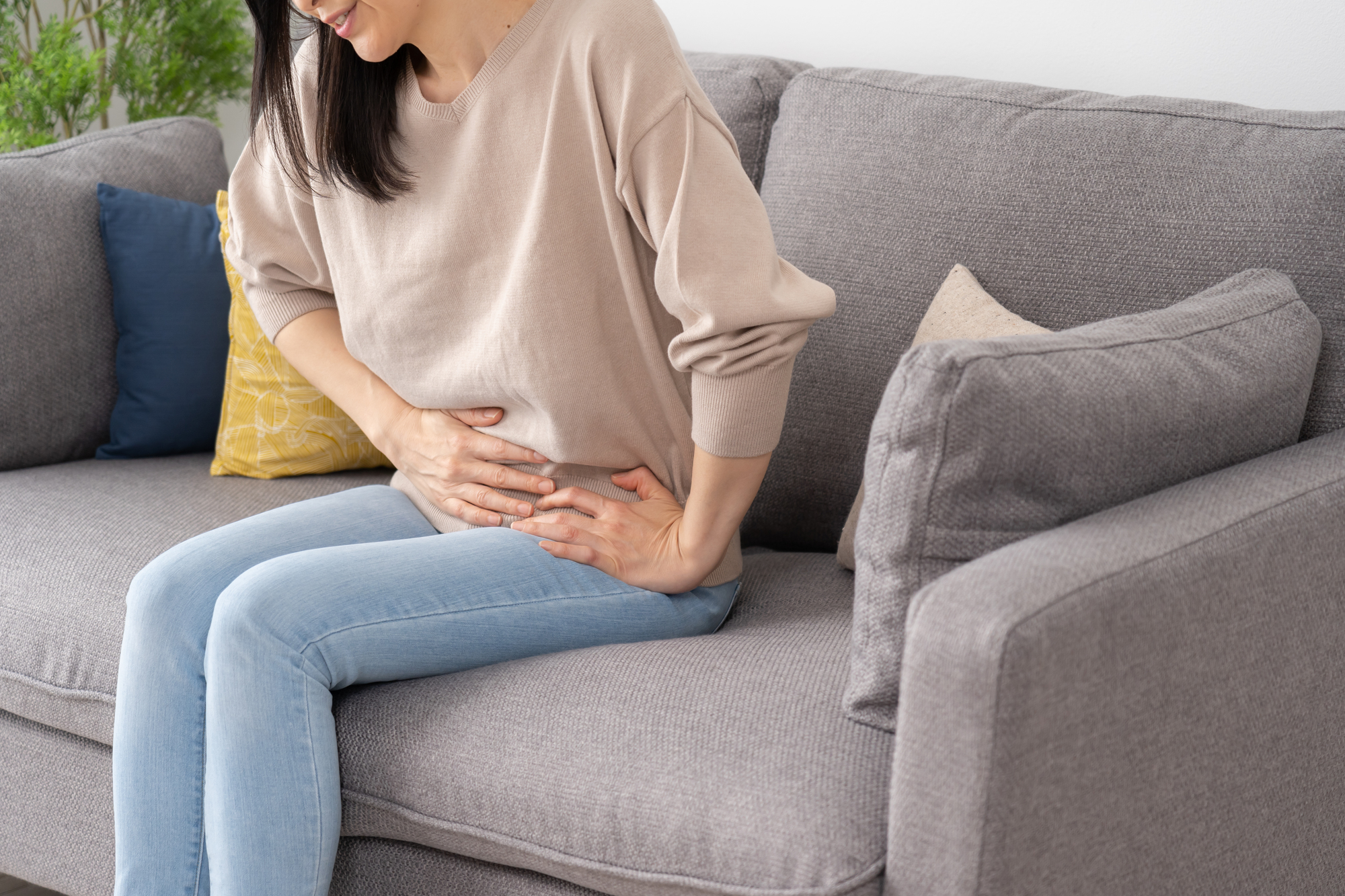
消化器は大まかに2つの部分に分けられます。1つ目は消化管と呼ばれ、口から食べ物を摂取して排泄するまでの経路です。この道には、栄養や水分の消化や吸収といった重要な役割があります。2つ目は肝臓、胆嚢、膵臓などからなる消化器で、ホルモンのコントロールや栄養の消化、代謝に関わる大切な役割を果たしています。
消化器のどちらかにでも異常があると、癌、糖尿病、肝硬変、下痢、腹痛を伴う腸の病気などが引き起こされ、日常生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。こうした状況では、主に内科的な治療が行われます。その治療を行うのが消化器内科です。
もし以下のような症状が現れる場合は、消化器に何かしらの異常が生じているかもしれませんので、放置せずに消化器内科を受診してください。
消化器内科で診療対象となる症状と疾患について
消化器内科で診る症状について
- 胃の不快感や痛み
- 吐き気や嘔吐
- 腹部の膨満感
- 背中・みぞおちの痛み
- 胸焼け
- 食欲が減った
- 便が細い
- 残便感や排便困難
- 下痢・軟便
- 便秘
- 血便・下血
- 全身倦怠感
- 体重の減少
- 目や皮膚が黄色い(黄疸)
- 健診・癌検診で異常を指摘された(バリウム検査での異常所見、便潜血での陽性、肝機能の異常、ピロリ菌検査での陽性など)
日常的によくある症状でも、細かく調べていくと深刻な疾患のサインとして現れている可能性もあります。このような場合、早期発見に繋がる可能性もあります。お腹に違和感・不調を感じられた場合をはじめ、どんな些細なお悩みでもお気軽にご相談ください。
消化器内科で診る疾患について
急性胃炎
急性胃炎は、胃粘膜が急速に炎症を引き起こす病気で、胃の違和感や激しい腹痛、吐き気などが生じます。進行すると胃潰瘍が発生し、血便や嘔吐が出るリスクが高まります。
急性胃粘膜病変(びらんが広範囲にできる)は、ストレスや刺激の強い食事、アルコールの過剰摂取、アレルギー、解熱鎮痛薬・抗生物質などの薬物によって引き起こされる異常です。
近年では、胃カメラ検査の使用が広まっているため、以前よりも粘膜の炎症状態を正確にチェックできるようになりました。
慢性胃炎・萎縮性胃炎
慢性胃炎は、胃の炎症状態が持続する疾患です。一方、胃酸や胃液を分泌する組織が減少した結果、胃粘膜が縮小してしまう疾患を萎縮性胃炎と呼びます。
胃炎が進行すると胃癌のリスクが高まりますが、ピロリ菌の除菌治療によって、胃癌のリスクを低減することは可能です。慢性胃炎の方は胃癌発症リスクが高いため、定期的に胃カメラ検査を受けるのが望ましいです。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、通常、食べ物を分解する際に役立つ胃酸や消化酵素が、胃や十二指腸に深刻な損傷を与える結果として発症する疾患です。主な原因としてはピロリ菌感染が挙げられますが、ストレスや薬物などが関与しているケースもあります。
これらの潰瘍は主に40代以上の方々に見られますが、ピロリ菌感染している若い世代の方々でも、発症することがあります。症状としては、お腹の膨満感、みぞおちや背中の痛み、胸やけ、吐き気などが挙げられます。
潰瘍が進行すると、出血が生じる場合もあり、それに伴い下血や吐血が起こることもあります。
胃癌
日本は他国に比べて胃癌の発症率が高く、そのほとんどは萎縮性胃炎から発症すると報告されています。発症の主な要因はピロリ菌感染ですが、塩分過多や喫煙、栄養バランスの偏った食事などによる影響も関与しています。
早期胃癌や特殊な種類の胃癌を発見するには、胃カメラ検査が必須です。近年では、内視鏡の診断と治療技術が向上しており、癌を早期発見し早期治療へ繋げることが、以前よりも容易になりました。定期的に胃カメラ検査を受けるように心掛けましょう。
ヘリコバクター・ピロリ感染症
 ヘリコバクター・ピロリ菌に感染すると、萎縮性胃炎を発症することがあります。そこからさらに悪化すると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、そして胃癌に移行するリスクが高くなります。
ヘリコバクター・ピロリ菌に感染すると、萎縮性胃炎を発症することがあります。そこからさらに悪化すると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、そして胃癌に移行するリスクが高くなります。
ピロリ菌は、幼少期に口内から菌が侵入した結果、胃の粘膜に生息し続けてしまう菌です。ピロリ菌を除去する除菌治療は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌の発症予防に有効です。
逆流性食道炎
逆流性食道炎は、胃の内容物と胃酸が食道へ逆流してしまうことで、食道粘膜に炎症が生じる疾患です。暴飲暴食、加齢、肥満、習慣飲酒、姿勢、食道裂孔ヘルニアなどの原因で、胃酸が過剰分泌したり逆流を防ぐ機能が落ちたりすることで発症します。
胃酸が食道から喉まで上がってくることで、胸焼けや喉のヒリつき、呑酸などが出現します。
食道癌
食道癌の主な原因として、喫煙や飲酒などが挙げられます。初期段階では自覚症状が見られませんが、進行すると食事中に喉のつかえ感や胸がしみる感覚といった症状が現れます。早期に発見することで、内視鏡治療などの侵襲の少ない治療でも治癒に期待できます。
喫煙・飲酒の習慣がある方やバレット食道の診断を受けた方は、定期的に胃カメラ検査を受けるのが望ましいです。
肝機能障害
肝臓に炎症が起こり、それにより肝細胞が破壊される疾患です。この障害が発症すると、ASTやALTなどの酵素が血液中に漏れ出てしまいます。これらの数値の異常は、血液検査で調べることが可能です。
肝機能障害の代表的な原因は、ウイルス性肝炎(主にB型やC型肝炎)、脂肪肝・非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、アルコール性肝障害、薬物性肝障害、自己免疫性肝炎などの疾患です。異常が見られた場合は、ぜひ消化器内科で診察を受けましょう。
脂肪肝やアルコール性肝障害の場合には、生活習慣を見直して肝機能を向上させていくと、進行が防ぎやすくなります。
脂肪肝
脂肪肝は、余分な糖質や脂質が中性脂肪に変わった結果、肝臓に中性脂肪が溜まってしまう(肝臓全体の30%以上を占める状態)疾患です。
脂肪肝の患者様のほとんどはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)も合併しており、これを無視すると肝機能がさらに悪化し、肝炎や肝硬変などの深刻な疾患に進展するリスクが高まります。また、脂質異常(高中性脂肪)や糖尿病などの生活習慣病を引き起こし、動脈硬化の進行リスクも高めてしまいます。このように、脂肪肝は健康に大きな悪影響を及ぼす疾患でもあり、早期発見と早期治療が必要とされている疾患でもあります。
慢性肝炎・肝硬変
肝臓の炎症が長期にわたって6カ月以上続くと、慢性肝炎とされます。この病気の主な原因はB型肝炎及びC型肝炎です。
日本では、慢性肝炎の発症のほとんどがC型肝炎ウイルスによるもので、その割合は70~80%です。一方で、B型肝炎ウイルスによるものは15~20%程度です。アルコールの過剰摂取や脂肪肝から慢性肝炎へ移行するケースもあります。慢性肝炎の治療は、その原因によって異なるため、1人ひとりに合った治療が重要です。
肝硬変は、慢性肝炎が進行し続けることで、肝臓内に線維組織が溜まって肝臓が硬くなる疾患です。この線維組織が溜まることで肝臓の組織は、正常な肝細胞から構成された柔らかい組織から、硬くてデコボコした組織に変化していきます。
肝硬変が悪化すると、肝機能が衰え、更に肝癌や肝不全などを合併するリスクが高くなります。このように肝硬変は、重篤な状態と言える疾患でもあるので、早めに発見し、適切な治療へ繋げていくことが重要視されています。
肝臓癌
肝細胞癌の代表的な原因は、ウイルス性肝炎、アルコール性肝炎、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)などです。この中で、約90%がB型肝炎やC型肝炎ウイルスなどのウイルス性肝炎によるものです。
ウイルス感染が持続すると、肝細胞が破壊されたり再生されたりする流れを繰り返します。そして、最終的には肝臓が硬くなり、肝硬変を招きます。この流れにより、癌を促進する「癌遺伝子」に加えて、本来癌化を抑制する働きを持っている「癌抑制遺伝子」にも影響を及ぼします。こういった遺伝子の変異が積み重なることで、肝細胞癌の発生リスクが上昇するのです。
長期間にわたる多量飲酒も肝細胞にダメージを与え、遺伝子の異常を引き起こすリスクを上昇させます。また、アルコールを飲んでいなくても、脂肪肝を引き起こし、肝臓の炎症から肝癌を発症させてしまう可能性は十分にあります。
近年、肝炎ウイルスの治療は進歩しているため、ウイルス性肝炎による肝細胞癌の発生は減少傾向にあります。しかし一方で、非アルコール性脂肪性肝疾患に関連している肝細胞癌は増えつつあります。
胆石(胆嚢結石症)・胆嚢炎
胆嚢結石(胆嚢に発生した結石)は一般的に、「胆石」と呼ばれています。胆石自体には症状はありませんが、胆石が胆嚢炎の原因となると、みぞおちから右の肋骨下にかけて激しい痛みが生じます。痛みは、背中や右肩にも広がる可能性があります。腹痛などの症状も伴っている場合は、消化器内科を受診されることをお勧めします。胆石は検診などで偶然発見されることが多く、無症状の場合は経過観察が選択されます。
急性膵炎・慢性膵炎
膵臓は、消化酵素を生成します。これには、炭水化物を分解するアミラーゼ、たんぱく質を分解するトリプシン、脂質を分解するリパーゼなどが含まれます。通常、これらの消化酵素は膵臓内で不活性型として生成され、自身の組織を消化しないよう働きます。急性膵炎は主にアルコール摂取や胆石が原因であり、主な症状には腹痛、背部痛、発熱があります。
しばしば、大量の飲酒などにより、消化酵素が膵臓内で活性化し、自己消化作用が働いてしまうことがあります。この状態は「膵臓の自己融解」と呼ばれます。このように急性膵炎は、消化酵素が急に激しく活性化し、膵臓を溶かしてしまう疾患なのです。
一方、慢性膵炎は、膵臓に繰り返し炎症をもたらす疾患です。主な原因はアルコールと喫煙とされています。消化酵素が少しずつ活性化することで、膵臓に炎症が起こります。炎症が何度も続くと、正常な膵組織が線維組織である間質に置き換わり、膵臓全体が硬化し、膵石が形成されることがあります。初期症状は主に腹痛ですが、病態が進行すると少しずつ膵機能が低下し、糖尿病や下痢(脂肪便)、黄疸などの症状が現れることがあります。
膵臓癌
膵臓癌には特有の症状が見られないため、早期発見は極めて難しいです。初期症状があっても、腹部の違和感や食欲不振、体重減少など、他の疾患でも見られる症状が多いです。進行すると、胃の不快感や腹痛、腰や背中の痛み、黄疸などの症状が起こります。
現時点では、はっきりとした発症原因は明らかになっていません。しかし、喫煙、糖尿病、慢性膵炎、膵臓癌の家族歴などが関連していると指摘されています。これらに該当する方は定期的に検査を受け、早期発見を目指しましょう。
便秘症
便秘症は複数のタイプに分類されており、大腸・直腸の問題が原因で起こる「機能性便秘」、便通が物理的に妨げられる(大腸癌・手術後の癒着・炎症性腸疾患など)ことによって生じる「器質性便秘」、全身疾患の症状として現れる「症候性便秘」、そして薬剤の副作用として生じる「薬剤性便秘」が挙げられます。
便秘の原因は多岐にわたり、それに応じて治療法も異なります。深刻な疾患によって引き起こされることもあるため、放置は禁物です。便秘で悩み続けている場合は、ぜひ診察を受けてください。
過敏性腸症候群
便秘や下痢が数カ月以上続き、腹痛や腹部膨満感などの症状も現れ、かつ検査しても異常が見つからない場合に疑われる疾患です。原因は特定されていませんが、ストレスや自律神経のバランスなど、心理的要因が関与している可能性があるとされています。
大腸癌
大腸癌は、主に大腸ポリープの進行によって発症する疾患です。また、大腸粘膜の炎症や、粘膜からの直接的な発症も考えられます。主に、食の欧米化や高齢化などが原因ではないかとされています。症状がほとんど目立たないまま進行する可能性があるため、早期発見には定期的な大腸カメラ検査が重要です。大腸ポリープが見つかれば、切除して将来の大腸癌リスクを軽減できます。大腸カメラ検査の必要性があれば、当院の本院である湘南いしぐろクリニック茅ヶ崎院へご案内します。
詳しい検査をご希望の方へ
 食道や胃、十二指腸、大腸、小腸、肛門の詳しい検査が必要と医師が判断しましたら、検査設備が整っております本院をご紹介させていただきます。
食道や胃、十二指腸、大腸、小腸、肛門の詳しい検査が必要と医師が判断しましたら、検査設備が整っております本院をご紹介させていただきます。