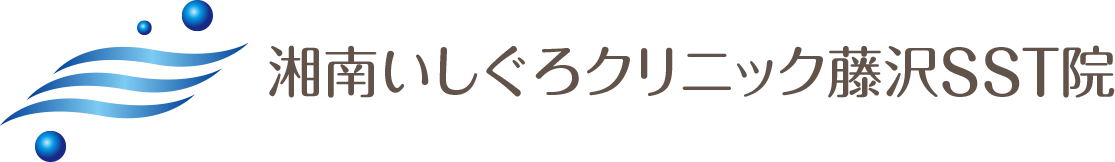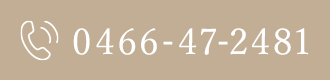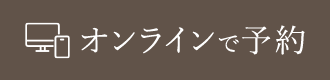- 高血圧(血圧が高いままの状態)について
- 高血圧の原因について
- 高血圧は症状が起きた時点で進行していることも:初期症状について
- 高血圧が進行することで発症する疾患について
- 高血圧の検査と診断方法について
- 高血圧において食事療法と運動療法は不可欠:治療法について
- 高血圧のリスクとコーヒーとの関係性:飲み方における注意点について
高血圧(血圧が高いままの状態)について
 高血圧症は、持続的に血圧が上がる状態です。血圧とは、心臓から送られる血液が血管壁に及ぼす圧力を指します。病院で血圧を測った場合、上限が140mmHg以上、下限が90mmHg以上になると高血圧と診断され、自宅での計測(病院よりも緊張しない状態で)では、上限が135 mmHg以上、下限が85 mmHg以上が目安とされています。自宅で計測すると、リラックスした状態で測定できるため、値が病院での測定よりも低くなる傾向があります。
高血圧症は、持続的に血圧が上がる状態です。血圧とは、心臓から送られる血液が血管壁に及ぼす圧力を指します。病院で血圧を測った場合、上限が140mmHg以上、下限が90mmHg以上になると高血圧と診断され、自宅での計測(病院よりも緊張しない状態で)では、上限が135 mmHg以上、下限が85 mmHg以上が目安とされています。自宅で計測すると、リラックスした状態で測定できるため、値が病院での測定よりも低くなる傾向があります。
柔らかい血管ですと、血圧の範囲は通常の値を示しますが、動脈硬化などにより血液循環が悪化すると、心臓からの血液量が増え、血管壁にかかる圧力が増加します。それにより、持続的に高い血圧が続いて高血圧症を発症する可能性が高まるのです。
高血圧の原因について
高血圧は、「本態性高血圧」という原因不明なものと、「二次性高血圧」という他の疾患により発症するタイプに分類されます。日本人は、ライフスタイルや遺伝の影響により、本態性高血圧の方が約90%を占めていると報告されています。
長時間にわたり、高血圧を放置すると血管壁が厚くなり、動脈硬化が進んでしまいます。その結果、血管が狭くなり血流が低下し、血流を促そうとして血圧が上昇しやすくなり、高血圧を発症しやすくなります。
遺伝
高血圧の原因の1つとして、遺伝があります。
親が高血圧であれば、その子供も高血圧になる可能性が高く、両親が高血圧だと子供の約半数が高血圧になると指摘されています。片方が高血圧の場合でも、子供の30%が高血圧を発症します。
なお、遺伝的要素だけでなく、体質や同じ食事をする習慣も影響しているのではないかとされています。
生活習慣や食生活による影響
塩分の過剰摂取
人間の体は塩分濃度を一定に保とうとします。過剰な塩分摂取は体が水分を増やし、塩分濃度を下げようとするため、血液量が増えて高血圧に繋がることがあります。
さらに、カリウムが豊富に含まれる野菜や果物の摂取量が不足すると、高血圧のリスクが高くなります。体内のナトリウムが過剰になっても、カリウムが不足していると、腎臓がナトリウムを排出できずに血液中の塩分が増えてしまいます。その結果、血圧が上昇することがあります。
運動不足
運動習慣が少ないと、体内の血流が低下し、血圧を上昇させるリスクが高まります。デスクワークの時間が長い方は、高いリスクを抱えているため、要注意です。
肥満
脂肪細胞は、血圧の上昇や動脈硬化を促進する物質を生成します。これにより、インスリンの効果が低下し、血中濃度が上昇し、交感神経が働いて血管を収縮させる恐れがあります。内臓脂肪型肥満、つまりメタボリックシンドロームの方は特に注意が必要です。肥満によって体重が増加すると、血液量も増加し、心臓に大きな負担がかかることになります。
ストレス過多
過度なストレスを感じると、交感神経が優位になります。その結果、心臓が収縮して心拍数が増加し、血液量が増えたり血管は収縮したりしやすくなります。
アルコールの過剰摂取
常にお酒を過剰摂取すると、血圧が上昇しやすくなり、中性脂肪が増えて動脈硬化のリスクも高まります。お酒を飲むことでストレスを解消でき、血圧も下がると考える方もいますが、過剰な飲酒は体に良くありませんので、摂取量には注意が必要です。
喫煙
タバコに含まれるニコチンは、交感神経を刺激し、血圧を上昇させる作用をもたらし、血管の収縮を引き起こします。さらに、活性酸素が増加し、動脈硬化を誘発します。
高血圧は症状が起きた時点で進行していることも:初期症状について
高血圧は初期段階では、動脈硬化が進んでいない限り、明らかな症状が出ません。それにより、発症に気づかないこともあるため、血圧を定期的にチェックすることが重要です。
症状が現れ始めたら、高血圧が悪化している可能性も考えられます。
高血圧の症状は、日本臨床内科医会で以下のように示されています。
- 頭痛
- 肩こり
- めまい
上記の症状は、高血圧以外の疾患でも起こり得るため、驚かれる方も多いかもしれません。
高血圧が進行することで発症する疾患について
 通常時、血管の壁には柔軟性がありますが、血圧が長期間高いままでいると、血管は常に緊張してしまいます。その結果、壁が厚く硬くなります。
通常時、血管の壁には柔軟性がありますが、血圧が長期間高いままでいると、血管は常に緊張してしまいます。その結果、壁が厚く硬くなります。
高血圧によって動脈硬化が促進されると、大動脈や小動脈の壁も厚く硬くなり、脳梗塞、脳出血、大動脈瘤、心筋梗塞、腎硬化症、眼底出血などの疾患のリスクも高まります。
さらに、心臓が血液量を増やそうと働いてしまうため、心肥大や心不全を引き起こすリスクも伴います。こういった危険な疾患を回避するためには、高血圧を予防することが肝要です。高血圧の方は、ご自身の血圧が基準値内になるよう気を付けましょう。
高血圧の検査と診断方法について
上腕部に「カフカ」を巻きつけ、血圧を測定する方法が一般的です。椅子に座り、リラックスした状態で、心臓と上腕が同じ高さになるよう調整して血圧を数回測定します。その平均値から、高血圧の有無を判断します。
高血圧の診断基準の内容
高血圧は、指標によって段階的に軽度から高度まで分類されます。
- 最高血圧140-159mmHg/最低血圧90-99mmHg:軽症高血圧
- 最高血圧160-179mmHg/最低血圧100-109mmHg:中等高血圧
- 最高血圧180mmHg以上/最低血圧110mmHg以上:重度高血圧
症状が深刻であるほど、日々の生活にも大きな影響を及ぼす可能性が高まります。重度高血圧に至ると、心不全や脳卒中など致命的な疾患の発症リスクが高くなるため、当てはまる方は要注意です。
高血圧において食事療法と運動療法は不可欠:治療法について
高血圧の治療には、「生活習慣の見直し」と「薬物療法」の2つが必要です。まずは生活習慣を見直すことから取り組んでいきます。これによって、高血圧だけでなく心臓病、脳卒中、糖尿病など多くの病気の改善に繋がるため、今後も役立つでしょう。
健康で豊かな人生を送るために、以下で解説する内容をぜひトライしてみてください。
生活習慣の改善方法について
塩分の摂取制限
昔の日本人は、塩分摂取が20gもあったため、脳卒中を引き起こすリスクが今よりも10倍も高かったという事実があります。このため、政府は減塩に力を入れるようになり、昭和62年ごろには11.7gまで減少しました。
しかし、最近ではハンバーガーやインスタント食品、ファストフードの普及により、再び塩分摂取量が増加していると指摘されています。
1日に摂取すべき塩分量の目安は約7gです。食事からは約3gの塩分が摂取されるため、調味料として塩や醤油を使用する場合は4g程度に抑えなくてはなりません。塩分摂取を抑えることで、カロリーも削減できます。それによって肥満問題も解決しやすくなります。
減量
「22×【身長(m)の2乗】」で、標準体重を求めることができます。多くの研究から、BMI22だと疾患リスクが低いことが分かっており、それを踏まえて計算式に組み込まれています。
肥満とは、「標準体重を20%超える状態」を指しますが、数値が基準内でも脂肪が特定の部位に蓄積すると、リスクが高まることがあります。内臓脂肪が過剰になると、運動や食事改善が不可欠になるため、基準範囲内であるからといって安心はできません。
さらに、体重と身長から計算されるBMI(ボディマス指数)がよく利用されます。
続けやすい運動
運動不足の方は、運動をする方と比べて、血圧が高くなると言われています。また、血圧を下げるためには運動療法が効果的であり、筋肉トレーニングなどの「静的な運動」よりも、「動的運動」である水泳やウォーキング、ランニングが効果的だと報告されています。
激しい運動は血圧を急上昇させる可能性があり、予期せぬ事故が起こるリスクも伴います。だからこそ、続けやすい軽い運動を習慣化することが重要だと言えるでしょう。
喫煙
喫煙と血圧は直接関係してはいませんが、動脈硬化を悪化させるリスクが最も高いのは喫煙です。血圧をコントロールすることは動脈硬化の予防に有効ですが、タバコを吸いながら血圧をコントロールしても大きな効果は見込めません。
また、精神的ストレスの感じやすさは、動脈硬化の進行と関係するとも言われています。
できる限り、ストレスは溜めないよう意識しましょう。ただし、精神的ストレスと血圧とのはっきりした関係性は未だに解明されていません。
さらに、気温の低い環境が血圧の上昇に繋がることがあります。血圧が高い方は、冬の気温の変化に気を付ける必要があります。具体的に言いますと、暖かい場所(リビングなど)から冷たい場所(トイレ、浴室など)に移動する際にも注意が必要です。
飲酒
アルコールと心臓・血管系の疾患との関係について、ご説明します。
確かに、アルコールを摂取することで心疾患を予防できる可能性はありますが、飲みすぎると脳卒中のリスクが高まるとも指摘されています。一時的ですが、アルコールを1回でも摂取すると、血圧は下がります。しかし、過剰な摂取はかえって血圧を上昇させ、血管系の疾患を引き起こすリスクが高くなります
また、アルコールを過剰に摂取すると、食生活が乱れ、体重管理が難しくなり、血圧が上昇する恐れもあります。日本酒は1合、ビールは500㏄以下を目安に、飲む量を調整してください。
薬物療法
高血圧を治療する場合、次のような4つの種類の薬が使用されます。
- 利尿剤:尿量を増やし、血液の量をコントロールする
- 血管拡張薬:血管の幅を広げる効果に期待できる
- 神経遮断薬:心臓への負担を減らし、血管の緊張を和らげる効果に期待できる
- レニン・アンギオテンシン系薬:昇圧ホルモンをコントロールし、利尿や血管拡張の作用をもたらす
これらの薬にはそれぞれメリットとデメリットがありますので、患者様の健康状態に考慮しながら処方します。
高血圧のリスクとコーヒーとの関係性:飲み方における注意点について
 近年の調査により、コーヒーと血圧の関係が明らかになりました。1日3~6杯のコーヒーを継続して飲む方とそうでない方を比較すると、前者の方がより、高血圧になるリスクが低いことが分かりました。
近年の調査により、コーヒーと血圧の関係が明らかになりました。1日3~6杯のコーヒーを継続して飲む方とそうでない方を比較すると、前者の方がより、高血圧になるリスクが低いことが分かりました。
コーヒーには抗酸化作用を持つコーヒーポリフェノール(クロロゲン酸)などが含まれており、酸化ストレスで損傷を受けた血管を修復し、血圧を下げる作用が期待されます。以前は、コーヒー中のカフェインにより、血中のアドレナリンが増加し、急激な血圧上昇が起こりやすいと考えられていましたが、この影響は一時的であり、コーヒーの摂取自体が高血圧を引き起こすわけではないということが分かっています。
1日3杯程度を目安にし、カフェイン摂取過多に気を付けつつ、コーヒーを楽しむ習慣を身につけましょう。肥満気味の方は、砂糖やミルクを過剰に入れないよう気を付けましょう。