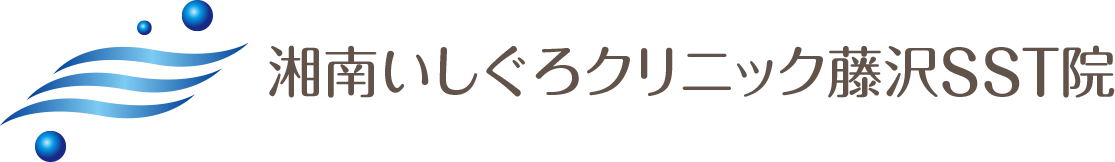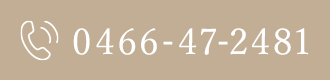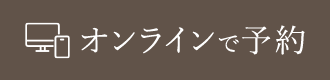過敏性腸症候群と診断基準について
 IBS(過敏性腸症候群)の診断には、国際的に認められている「ローマ基準(Rome Criteria)」が用いられます。
IBS(過敏性腸症候群)の診断には、国際的に認められている「ローマ基準(Rome Criteria)」が用いられます。
この基準は、IBSに特有の症状を明確に定義するためのものです。 ローマ基準による診断には、以下の条件が必要とされています。
- 過去3カ月の間に、月4日以上の頻度で腹痛または腹部の不快感が繰り返し現れている
- その症状が、以下のうち2つ以上に関連していること
- 排便によって症状が軽減する
- 排便の回数が変化している
- 便の形状や硬さに変化がある(便秘や下痢など)
- こうした症状が、少なくとも6カ月以上前から続いていること
これらの条件を満たす場合、IBSの可能性が考えられます。
ただし、IBSと似た症状を示す他の疾患もあります。これらの疾患と鑑別するためには、詳細な問診、身体所見、必要に応じた検査が不可欠です。
正確な診断を得るためには、専門の医師による評価を受けることが重要です。
過敏性腸症候群のタイプについて
IBS(Irritable Bowel Syndrome、過敏性腸症候群)は、症状の現れ方によって主に3つのタイプに分類されます。
下痢型(IBS-D:Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea)
頻繁な排便とともに、柔らかい便や水っぽい便が続くのが特徴です。腹部の痛みや不快感を伴うこともあります。
便秘型(IBS-C:Irritable Bowel Syndrome with Constipation)
排便が困難、不規則といった症状が中心となるタイプです。便通が滞りがちで、腹部の張りや痛みを感じることがあります。
混合型(IBS-M:Irritable Bowel Syndrome Mixed)
下痢と便秘が交互に現れるタイプで、便通のパターンが安定せず、日によって症状が変化します。
なお、IBSの症状は人によって異なり、必ずしもこれらの分類に明確に当てはまるとは限りません。また、時間の経過とともに症状のタイプが変化することもあります。
過敏性腸症候群の治療について
IBSの治療は、患者様1人ひとりの症状や体調に応じて、複数の手法を組み合わせて進めるのが一般的です。症状のタイプや生活背景を踏まえながら、以下のような対策が検討されます。
生活習慣の見直しについて
食事の工夫
症状を悪化させる食材があるため、食べるものの選び方や食事のタイミングを調整することが大切です。
こまめな食物繊維の摂取
腸の働きを整えるためには、適量の食物繊維を日々の食事に取り入れることが有効です。
水分補給
十分な水分を摂ることで、排便がスムーズになりやすくなります。
ストレスへの対処
強いストレスがIBSの症状に影響することがあるため、心身を落ち着かせる習慣を取り入れることが重要です。 マインドフルネスやヨガなどのリラクゼーション法が役立つ場合もあります。
薬物療法について
抗下痢薬
下痢型の患者様に処方されることがあります。
緩下剤
便秘型の患者様に処方されることがあります。
抗けいれん薬
腹痛を軽減する目的で、腸の過剰な収縮を抑える薬が使われることがあります。主に便秘型の患者様に使用されます。
プロバイオティクス
腸内環境を整えるために、有効となる菌を補う医薬品が活用されることがあります。
メンタルケアについて
 心理カウンセリングや精神療法を取り入れることで、心の緊張や不安感を和らげ、IBSの症状が軽減されることがあります。
心理カウンセリングや精神療法を取り入れることで、心の緊張や不安感を和らげ、IBSの症状が軽減されることがあります。
こうしたアプローチは、症状のコントロールを助けるだけでなく、QOLを高めるうえでも有効です。
ただし、IBSの治療は1人ひとり異なるため、個々の状態に合わせたオーダーメイドの治療計画を立てることが大切です。