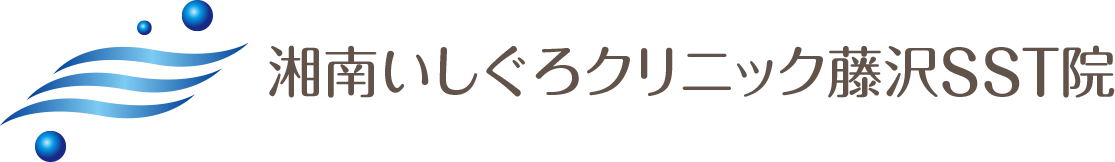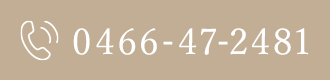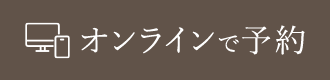当院の内科について

当院では、高血圧や脂質異常症、糖尿病、痛風(高尿酸血症)などの生活習慣病をはじめ、その他の慢性疾患や喉の痛み、腹痛、発熱、下痢、吐き気、嘔吐といった急性症状、風邪、インフルエンザ、気管支炎、逆流性食道炎、胃腸炎、胃十二指腸潰瘍など、多くの方が経験する症状や疾患まで、幅広く診療していきます。
「気分が優れない」「色々症状がある」「症状が続いていて良くならない」「どの診療科で相談すればいいのか分からない」などでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
内科で診療対象となる症状・疾患について
- 喉の渇き
- 喉の痛み
- 咳
- 痰
- 腹痛
- 胃の痛み
- 発熱
- 便秘
- 下痢
- 吐き気
- 嘔吐
- 動悸
- 易疲労性(疲れやすい)
- イライラしやすくなった
- なんとなくやる気が出ない
- 呼吸がしにくい
- 食欲がコントロールできない
- 食欲が減った(食欲不振)
- 体重が増えた
- 体重が減った
- 膨満感がある
- 寒がり
- 暑がり
など
生活習慣病とされる疾患について
高血圧症
 血圧は気温の変化や運動、ストレスなど様々な要因により、常に上がったり下がったりするのを繰り返します。
血圧は気温の変化や運動、ストレスなど様々な要因により、常に上がったり下がったりするのを繰り返します。
高血圧は、血圧が慢性的に高い状態を指し、病院で計測した場合は140/90mmHg以上、ご自宅で計測した場合は135/85mmHg以上が基準となります。
ご自宅で計測する際はリラックスできるため、血圧が通常よりも低くなる可能性があります。
高血圧が悪化すると、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。したがって、高血圧と診断されたら、速やかに治療を受けて血圧をコントロールするよう心がけましょう。
糖尿病
 血糖値が過剰に高くなると、高血糖になります。その状態が慢性化すると糖尿病に進行します。膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの機能が低下することで発症し、細胞がエネルギー源として糖を吸収しにくくなります。
血糖値が過剰に高くなると、高血糖になります。その状態が慢性化すると糖尿病に進行します。膵臓から分泌されるインスリンというホルモンの機能が低下することで発症し、細胞がエネルギー源として糖を吸収しにくくなります。
糖尿病は初期症状が分かりにくく、進行すると疲れやすさや喉の渇き、頻尿などが見られます。
また、傷の治りが遅くなり、感染症のリスクも上昇します。さらに、高血糖が持続すると動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞のリスクを高め、毛細血管の狭窄や閉塞、破裂などの重篤な合併症を招く原因にもなります。このような合併症として、糖尿病性神経障害や糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症などが挙げられます。
残念ながら糖尿病は根治に期待できない疾患です。しかし、適切な治療を継続し血糖コントロールを行っていけば、動脈硬化や先に述べた合併症の発症・進行を防ぐことは可能です。
それ故に、早期発見・早期治療が重要視されています。
健康診断などでHbA1cやグルコースの異常が見られた場合は、速やかに受診し治療を受けましょう。35歳を過ぎると糖尿病の発症リスクが上昇するため、自覚症状が見られなくても定期的に検査を受けるのが望ましいです。
脂質異常症
 血液中には中性脂肪(トリグリセライド/TG)やコレステロールなどの脂質が含まれております。これらが基準値よりも増加したり、バランスが悪くなったりすると、動脈硬化の発症や進行のリスクが高まります。
血液中には中性脂肪(トリグリセライド/TG)やコレステロールなどの脂質が含まれております。これらが基準値よりも増加したり、バランスが悪くなったりすると、動脈硬化の発症や進行のリスクが高まります。
これまで、脂質異常症は「高脂血症」と称され、単に脂質の増加のみに焦点が置かれていました。
しかし、近年では研究が進み、血液中の余分な脂質を吸収する機能の低下も、動脈硬化の原因となることも分かるようになりました。
その結果、脂質の異常値が見られる状態を「脂質異常症」と称するようになりました。
食事療法などの治療を早く始めるほど、心筋梗塞などのリスクが軽減できますので、早めに受診と定期的な検査を受ける様にしましょう。
痛風(高尿酸血症)
 血液中の尿酸値が基準値を超え、その状態が長期間続いてしまう疾患です。
血液中の尿酸値が基準値を超え、その状態が長期間続いてしまう疾患です。
ほとんどの場合、症状が自覚されることはありませんが、この状態が慢性的に続くと、尖った尿酸結晶が関節に溜まり、痛風を招くリスクが高くなります。
さらに、腎臓疾患や尿路結石、最悪の場合には脳卒中や心筋梗塞を発症することもありますので、早期のうちに確実な治療を受けることが重要です。尿酸値に付いて指摘された場合は、こまめに検査や治療を受け、尿酸値をコントロールしましょう。
その他の内科系疾患について
風邪(感冒)
 一般的には喉の痛み、鼻水、咳、発熱などの症状が現れる疾患のことを指します。
一般的には喉の痛み、鼻水、咳、発熱などの症状が現れる疾患のことを指します。
原因の多くはウイルスに由来し、ウイルスが上気道に侵入して炎症を起こすことが知られています。
風邪の誘因は疲れやストレス、寝不足などによる免疫力の低下や、気温の変化、乾燥、冷気などが挙げられます。
症状は一週間程度で改善することが多いですが、十分な休息と栄養摂取、体を冷やし過ぎないことが重要です。症状が長引く場合は、早めに医師の診察を受けるようにしてください。
インフルエンザ
 インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症です。主に2つあり、主に冬季に流行する季節性インフルエンザと、豚や鳥から感染する豚インフルエンザウイルス・鳥インフルエンザウイルスなどからくる動物型インフルエンザに大別されます。
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる感染症です。主に2つあり、主に冬季に流行する季節性インフルエンザと、豚や鳥から感染する豚インフルエンザウイルス・鳥インフルエンザウイルスなどからくる動物型インフルエンザに大別されます。
さらに、インフルエンザウイルスは3タイプあり、A型、B型、C型に分けられます。A型は動物及び人間に感染し、季節性インフルエンザの主たる原因として知られています。一方、B型は主に人間に感染し、季節性インフルエンザの原因として認識されています。C型の流行は極めて珍しく、感染しても比較的軽い症状で治まるケースがほとんどです。
アレルギー
 アレルギーは、全身に影響を及ぼす可能性があり、その症状も多岐にわたります。ただ、特に鼻や目、皮膚など、外部と接する部位に現れやすいため、これらの箇所での症状が一般的とされています。
アレルギーは、全身に影響を及ぼす可能性があり、その症状も多岐にわたります。ただ、特に鼻や目、皮膚など、外部と接する部位に現れやすいため、これらの箇所での症状が一般的とされています。
主な症状には、2週間以上続く乾燥した咳、透明で水っぽい鼻水、原因不明の湿疹・蕁麻疹、腹痛、下痢、嘔吐などの消化器症状、急激な息苦しさや呼吸困難、舌のザラつきによる不快感などが挙げられます。
アレルギー性鼻炎(通年性・季節性)
アレルギー性鼻炎のタイプについて
アレルギー性鼻炎とは、アレルゲン(アレルギー症状の原因となる物質)が鼻の粘膜に付着し、アレルギー反応を引き起こすことで、鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状を引き起こす疾患です。2つのタイプに分けられ、それぞれ以下のような特徴を持っています。
通年性アレルギー性鼻炎
ハウスダスト及びカビ、ダニなどが原因とされている鼻炎です。一年中症状が現れます。
季節性アレルギー性鼻炎
一般的に「花粉症」と呼ばれるものです。春は主にヒノキやスギが原因ですが、春以外の季節でも、ヨモギ、ブタクサ、シラカンバなどによって発症することがあります。
検査・診断方法について
血液検査によって、まずアレルギー体質かどうかや、ヒノキやスギなどの特定のアレルゲンに対する抗体の有無などをチェックします。検査結果が判明できるまで、数日程かかります。
治療方法について
主に薬物療法が行われます。患者様の症状に合わせて、内服薬や点眼薬、点鼻薬などを処方させていただきます。
当院では、どのような薬も処方可能です。内服薬については、「眠くなりやすい」というイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、近年では眠気が出にくい薬も普及されています。
膀胱炎
 膀胱粘膜が炎症を起こす疾患です。頻尿や排尿時の痛み、残尿感などの症状が見られます。膀胱炎の原因のほとんどは、細菌感染によるもので、特に女性に多く発症する傾向があります。
膀胱粘膜が炎症を起こす疾患です。頻尿や排尿時の痛み、残尿感などの症状が見られます。膀胱炎の原因のほとんどは、細菌感染によるもので、特に女性に多く発症する傾向があります。
女性の体の構造上、尿道が短く、尿道口と肛門が近いため、細菌の侵入が容易となっています。
症状が改善しても炎症が残存していると、再発するリスクは高いままで、再発が繰り返されると腎盂腎炎などの深刻な疾患を引き起こす恐れがあります。それ故に、早期の発見と治療が極めて重要とされています。
過活動膀胱
 過活動膀胱を発症すると、突然強い尿意を感じる「尿意切迫感」や、頻繁にトイレへ行く「頻尿」、尿意で夜目が覚めてしまう「夜間頻尿」などが現れます。
過活動膀胱を発症すると、突然強い尿意を感じる「尿意切迫感」や、頻繁にトイレへ行く「頻尿」、尿意で夜目が覚めてしまう「夜間頻尿」などが現れます。
膀胱内に尿が十分に蓄積される前に、膀胱が収縮してしまうことが原因とされています。
過活動膀胱は、40歳以上の約12%の方がかかっていると報告されているように、決して珍しい疾患ではありません。
主な原因としては、神経障害、前立腺肥大、加齢による膀胱機能の変化などが挙げられますが、特発性のもの(原因不明)もあります。過活動膀胱は適切な治療で改善が期待されます。年齢を理由に諦めず、症状でお悩みの場合は遠慮なくご相談ください。