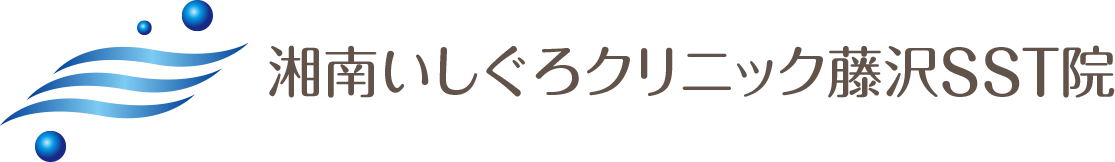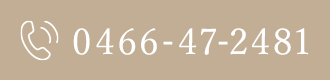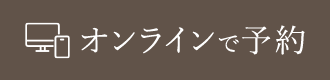当院の呼吸器内科について

呼吸器科は、鼻や喉(咽頭・喉頭)、気管、気管支、肺など、呼吸に関連する部位の症状及び病気をメインに診る所です。
特にコロナ禍では、コロナウイルスの感染が呼吸器感染症としても認識されており、重症コロナ感染症に伴う肺障害は、命に関わる状態とされています。人工呼吸管理やECMOなどが必要であり、注目される治療分野の一つとされています。
風邪や扁桃炎、咽頭炎、気管支炎、肺炎、肺気胸、マイコプラズマ感染症などの急性疾患をはじめ、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺結核、気管支拡張症などの慢性疾患も診療対象となります。
他の疾患と同様に、肺は一度損傷を受けるとほぼ再生しない臓器であり、損傷が重いほど、それに付随する障害を一生涯受け入れなくてはならなくなります。
さらに、呼吸は人間にとって不可欠なもので、常に行われている行為です。これが損なわれると、息切れや咳、痰などが起こり、日常生活の質を低下させる可能性があります。
呼吸器の疾患には、なかなか治らないものも多くありますが、早期に見つけて治療を始めることで、大きな問題なく一生を長く過ごすことも可能です。
そのためには、気になる症状が出たら1日でも早く受診し、検査を受けるように心掛けましょう。
当院では呼吸器内科のエキスパートとして、これらの呼吸器疾患の検査、診断、治療、そして慢性疾患の管理を行っております。
前に述べた通り、どの疾患においても、早期発見・早期治療は不可欠とされています。そのために必要な機器もございますが、当院では気管支鏡検査以外の侵襲の少ない検査にもほぼ対応しております。
呼吸器の症状でお悩みの方は、お気軽に当院へご相談ください。
よく見られる呼吸器症状について
 呼吸器トラブルは、呼吸音である程度分かることがあります。例えば、咳や痰、または「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音の異常を感じることがあります。肺と呼吸器は、体の生命維持のために酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する重要な働きを担っているため、このプロセスが妨げられると、息切れや呼吸困難、チアノーゼなどの状態に陥る恐れがあります。
呼吸器トラブルは、呼吸音である程度分かることがあります。例えば、咳や痰、または「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音の異常を感じることがあります。肺と呼吸器は、体の生命維持のために酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する重要な働きを担っているため、このプロセスが妨げられると、息切れや呼吸困難、チアノーゼなどの状態に陥る恐れがあります。
炎症がひどい場合は、胸の痛みや発熱も起こる可能性があります。もちろん、これらの症状は、呼吸器以外の問題でも発生する可能性がありますが、当院はあらゆる疾患を検討しながら、細やかな診察を実施します。呼吸器関連の症状が悪化すると、命に影響を及ぼす危険性があります。
咳
咳は、気管に入り込んだ異物を体外に追い出すための生理学的に不可欠な行動であり、健康な方でも、僅かな刺激で起こる症状です。
実は、咳がない状態は危険であり、誤嚥性肺炎や異物誤嚥による窒息のリスクが高まってしまうのです。
ただし、咳が続くことで仕事や睡眠に悪影響を及ぼしている場合は、迅速な処置が不可欠です。
特定の時期や場所で咳が発生したり、風邪を引いていないのに痰が絡んだりする場合は、呼吸器疾患による咳の可能性が疑われます。
食事中にむせたり咳き込んだり、食事を終わらせるスピードが遅くなったりすると、気管に食べ物などが入る「誤嚥」の可能性が考えられます。特に、高齢者は飲み込みが弱くなるため、誤嚥のリスクが高くなります。誤嚥による肺炎は誤嚥性肺炎と呼ばれ、重度の肺炎を引き起こすこともありますので、このような症状が現れた際には、どうぞ当院へご相談ください。予防や将来的な対応についても、長期的なアプローチとご相談をいただく必要があります。
痰・血痰
痰は、気管支や肺から異物を排出するための生理的な反応の一環であり、健康に問題のない方でも起こり得る症状です。ただし、病気にかかっていないにもかかわらず、特定の姿勢をとったり、お風呂に入ったり、夜寝ると必ず発生したり、発熱や咳と共に常に見られたりしている場合は、注意しなくてはなりません。
特に、痰に血が混じっていたり、黄色・緑色・茶色の痰が排出したりした場合には、速やかに医療機関へ相談してください。また、痰の量や頻度が増えた場合も、呼吸器疾患のサインかもしれませんので、速やかに医師の診察を受けましょう。
息苦しさ
息苦しい症状は、重い症状や加齢による変化、精神的な要因など、様々な要素によって起こります。個々の感じ方にも影響されるため、その深刻さや危険性を判断するのは困難な場合があります。
ただし、どの状況でも、低酸素血症からくる息苦しさは病的であり、警戒が必要です。
通常、身体を動かしている時や安静時でも、摂取する酸素量が消費する量を上回らないと、体内の酸素が不足し、息切れや息苦しさが現れます。特に激しい運動時には、酸素の消費が多くなり、息切れが起こりやすくなります。ただ、これは健康な方にも起こりうる生理現象ですので、あまり心配する必要はありません。
しかし、運動中に息苦しくなったり、坂道や階段で息が詰まったり、休んでいても息苦しくなったりした場合は、何らかの異常が疑われるため、迅速に呼吸器内科へ受診してください。
喘鳴(ぜんめい)
呼吸する空気の通り道に何らかの障害が生じ、狭くなることで「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という呼吸音が聞こえる状態です。気管支喘息やたばこ病(COPD)の発作だけでなく、異物の誤嚥時にもこの症状が現れることがあります。喘息やたばこ病(COPD)の治療中に喘鳴が見られた際には、発作が発生している可能性が考えられます。その場合は初めに、処方された発作止めの薬を使用して、喘鳴を和らげましょう。1日程度経過を観察しても症状が改善しない場合は、再び診察を受けていただく可能性があります。また、喘息でない方で喘鳴が聞こえた場合は、迷わずに医療機関へ受診しましょう。
胸痛、背中の痛み
胸痛は、呼吸器や心臓、消化器など、様々な部位の疾患のサインとして現れることがあります。ただし、肺に異常があっても胸が痛むという症状は滅多に起こりません。これは、肺を覆う胸膜以外に、痛覚を感じる器官が少ないためです。そのため、胸が痛む時には、まず心筋梗塞や狭心症など、緊急を要する心臓の疾患がないかを検査します。その次に、気胸や胸膜炎、膿胸など、迅速な対処が必要な呼吸器疾患があるかどうかをチェックします。
当院では、問診や心電図の異常から心臓の疾患の可能性が高いと判断された場合には、適切な検査や治療を受けるため、専門医療機関をご紹介します。
発熱
他の症状の有無についても考慮した上で、問診や検査を実施します。発熱の推移や程度、呼吸器の状態や他の不調を確認した後、必要な検査を受診していただきます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、現在は発熱外来を設置して診療しています。
いびき・昼間の強い眠気
「いびきについて家族から指摘された」「昼になると眠くなって辛い」というお悩みはございますか?これらの症状が顕著に現れる場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いです。
睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中における無呼吸や低呼吸により、睡眠の質が低下する疾患です。特に、アルコール摂取後や肥満、顎が小さい方に多い傾向があります。この状態を放置すると、血管疾患に進展する可能性があります。具体的には高血圧、糖尿病、心臓疾患が挙げられます。これらの疾患は一度発症すると完治が難しいため、早急な対応が不可欠です。
さらに、日中の眠気が継続的にひどい場合、最悪の場合には交通事故など重大な問題を引き起こす危険性もあります。そのため、早期の診断と適切な治療が不可欠です。
よく見られる呼吸器疾患について
風邪症候群
風邪症候群は、急性上気道炎と呼ばれることもあります。ウイルスが上気道(鼻、喉、気管など)に侵入し、炎症が起こってしまう疾患です。
通常、数日~1週間で症状が緩和されます。鼻水やくしゃみ、発熱、喉の痛み、咳、痰、頭痛などの症状が起こり、嘔吐や下痢、腹痛などの消化器症状を伴うケースもあります。
代表的な原因はウイルス感染で、その場合は抗菌剤を用いてもなかなか改善できません。なお、細菌感染が疑われる場合には抗菌剤の使用が検討されます。さらに、治療は主に、症状の緩和を目指すために行われます。
インフルエンザ
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって発症する感染症です。高熱や頭痛、悪寒、関節痛、全身の倦怠感、咳、痰、呼吸困難、腹痛、下痢などの症状が現れます。風邪よりも症状が強く、気管支炎や肺炎、脳炎、心疾患などの合併症を招くこともあります。
発症と悪化を予防するためには、定期的な予防接種が有効です。万が一感染した場合は、周囲に感染させないよう安静にして過ごしましょう。症状が重い場合は、適切な薬で症状を和らげます。特に感染初期では、ウイルスの増殖を抑制する薬が有効です。
気管支炎
気管は、左右の主気管支から分岐しており、そこから更に細かい気管支が存在している器官です。気管支炎は、上気道炎の症状に由来して起こるものですが、それによって炎症が広がることで発症するケースもあります。主な症状には、咳や痰、発熱、全身の倦怠感、食欲不振などが挙げられ、悪化すると肺炎を発症する恐れもあります。細菌感染による場合は抗菌薬が処方され、インフルエンザによる場合は抗ウイルス薬が使用されます。
肺炎
ウイルスや微生物が肺に感染し、炎症を引き起こす疾患です。高齢者や慢性疾患を抱える方は、免疫力が低下しているため、症状が重くなりやすい傾向があります。また、子供や若年層はマイコプラズマという細菌によって発症することもあります。
一般的な症状には、発熱や咳、痰、胸痛、息苦しさなどがあります。特に細菌による肺炎の場合は、速やかに抗生物質を服用して治療する必要があります。また、血中の酸素濃度が不足していても、息苦しさを感じないケースも存在しています。症状が重くならないよう、発熱や咳が現れた場合は、迷わずに医療機関へ受診してください。
咽頭炎
咽頭とは、鼻や口の奥に位置する喉の上部です。外部からの空気に晒されやすく、細菌、ウイルス、有害物質(ガスやほこり、タバコの煙など)、声の出しすぎなどの影響に左右されます。
主な症状には、喉のかゆみや痛み、声のかすれ、咳、痰などがあります。症状が悪化すると気道が狭くなり、呼吸困難に陥ることがあるため、迅速な治療が重要です。風邪と同様に、対症療法が行われますが、気道が狭窄していたり急性喉頭蓋炎を発症していたりしている場合は、点滴などの治療が不可欠です。
扁桃炎
口蓋扁桃(喉の奥にある部位)が感染することで、急速に炎症が引き起こされる疾患です。口を開けると、赤く腫れた扁桃や白い膿が見られることがあります。喉の痛み、頭痛、寒気、高熱、関節痛、倦怠感などが典型的な症状です。
ウイルスによって発症している場合は、風邪と同様に症状を緩和する対症療法を選択します。細菌が原因の場合は、抗生物質が必要です。喉の痛みを和らげるために、うがいを行うことも心がけましょう。
睡眠時無呼吸症候群について
 睡眠時無呼吸症候群は、夜寝ている時に呼吸が停止し、昼間に異常な眠気が生じる病気です。2003年の山陽新幹線の運転手による居眠り運転事故や2012年の大型バスツアーの事故などにより、一般の方にも広く認知されるようになりました。
睡眠時無呼吸症候群は、夜寝ている時に呼吸が停止し、昼間に異常な眠気が生じる病気です。2003年の山陽新幹線の運転手による居眠り運転事故や2012年の大型バスツアーの事故などにより、一般の方にも広く認知されるようになりました。
交通事故以外にも、学業成績低下や業績の不振、高血圧、狭心症、糖尿病のリスク、そしてうつ病など、他の疾患との関連が指摘されています。中等度から重度の未治療の睡眠時無呼吸症候群では、8年後の生存率が約60%という統計データも存在しています。CPAP治療を適切に行うことで、平均水準に保つことが示されています。
「いびき」や「昼間の眠気」だけでなく「成績の低下」や「朝起きられない」などの症状でお悩みの場合は、ぜひ当院へご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群の原因について
睡眠時無呼吸症候群の原因は大きく分けると2つあり、中枢性と閉塞性に大別されます。一番多いのは閉塞性です。この症状は、気道が遮られることで起こります。肥満の方が該当しやすいと思われがちですが、痩せ型の方にも発症するケースはあります。
- 肥満
- 首が短い
- 顔が小さい、顎が小さい
- アルコールを常習的に飲んでいる
- 舌が口に対して大きい
- 扁桃腺が大きい
当院における検査方法について
患者様のご自宅で、簡単に行えるアプノモニターによる簡易検査を手配させていただきます。
ご自宅で行った検査結果を分析し、当院で結果の説明を行います。
状態によっては、より詳細な検査が必要になる方もおられます。
その際には、当院の本院である湘南いしぐろクリニック茅ヶ崎院をご紹介いたします。
睡眠時無呼吸症候群の治療方法について
ダイエット(減量)
肥満の方はまず、体重を減らしましょう。体重を減らすと、血圧や糖尿病も予防しやすくなります。1人でダイエットすると挫折しそう、長続きしないなどのお悩みがある場合は、お気軽にご相談ください。一緒に取り組んでいきましょう。
CPAP療法
就寝時に機械と繋がったマスクを装着し、そのまま眠っていただく療法です。眠っている間に、狭くなった気道に圧力をかけて確保します。
治療を受けたばかりの段階では、違和感が生じるかもしれませんが、設定やマスクのフィッティングを調整することで、徐々に慣れていく方が多いです。
CPAP療法は正しく活用することで、予後の改善にも繋がりやすくなります。「4時間以上使用し、日数70%以上」を目指しながら、一緒に取り組んでいきましょう。
マウスピース
マウスピースを使うことで顎の位置を調整し、気道を確保して無呼吸を防ぎます。
軽症の睡眠時無呼吸症候群では一定の効果が見込まれますが、重症の場合は効果が期待できない可能性が高いため、重症の方にはお勧めできません。マウスピースを作成する際には、対応できる歯科医をご紹介します。
外科治療
扁桃腫大やアデノイドにより、喉の奥が物理的に狭くなっている際には、手術による治療を提案することがあります。
気管支喘息について
 気管支喘息とは、風邪や呼吸器疾患、気候の急激な変化、アレルゲン、運動などによって引き起こされ、気管支(気道)が慢性的に炎症することで、気道が狭くなり、咳や喘鳴、呼吸困難などの呼吸器の異常が発生する疾患です。
気管支喘息とは、風邪や呼吸器疾患、気候の急激な変化、アレルゲン、運動などによって引き起こされ、気管支(気道)が慢性的に炎症することで、気道が狭くなり、咳や喘鳴、呼吸困難などの呼吸器の異常が発生する疾患です。
気管支喘息の症状について
気管支喘息が起こると、下記のような症状が現れます。
- 喘鳴が聞こえる(ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音)
- 夜や早朝になると咳が出る
- 息苦しさを感じる(呼吸困難)
気管支喘息の原因について
気管支喘息の患者様は気道が慢性的に炎症するため、刺激に敏感に反応し、発作を引き起こすアレルゲンが体内に入ると、過剰な免疫反応(抗原抗体反応)が起こり、喘息発作が発生します。発作に伴い気道が狭くなり、空気が通りにくくなるため、息苦しさなどの呼吸困難の症状が現れます。
発作のトリガーとなるアレルゲン
- カビ
- ダニ
- ハウスダスト
- ペットの毛
- 花粉
- ウイルス
発作を招く要因・行動
- カビ
- ダニ
- ハウスダスト
- ペットの毛
- 花粉
- ウイルス
気管支喘息の診断方法について
咳や呼吸困難が生じる原因疾患は多岐にわたるため、問診では症状に加えて、アレルギー歴や喘息の既往歴・家族歴などをお伺いします。そこから要因を絞り込み、判断して参ります。聴診や胸部レントゲン、肺機能検査、採血検査などで診断を行って参ります。
気管支喘息の治療方法について
気管支喘息の治療には薬物療法が行われます。主に、発作を予防する発作予防薬と、発作が発生した際に抑制する発作治療薬の2つの薬を使用します。近年では、喘息発作を回避する治療がメインとなっております。
発作予防薬
気管支(気道)が狭くなり、喘息の発作を防ぐために、そして免疫反応を抑制するため、吸入ステロイドが使用されます。約30年前から使用されており、喘息による死亡者数が大幅に減少したというデータが存在します。
近年では、ステロイド吸入だけでなく、長時間持続する気道拡張薬(β₂刺激薬)の組み合わせが中心になっています。この組み合わせにより、喘息の発作をかなり予防できるようになってきています。
発作治療薬
発作が起こり、咳や呼吸困難などの症状が現れた場合に症状を抑えるために使用します。当院では、サルタノールやメプチンなどの吸入タイプの薬も用意しております。
禁煙を勧める理由について
近年では、喘息による死亡例が大幅に減少しましたが、タバコを吸っている方は要注意です。 吸入ステロイドの効果が低下し、肺気腫や慢性気管支炎(COPD)などの肺及び気道の炎症が重なることで肺機能が低下します。 普段からタバコを吸っている方は、治療を機に禁煙を検討しましょう。