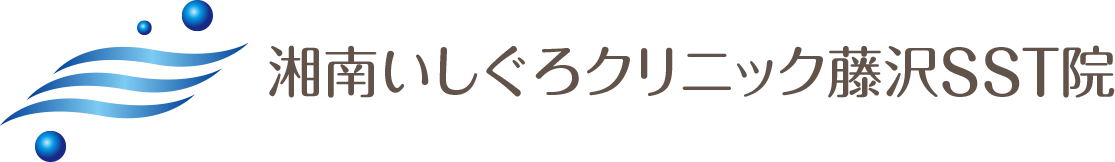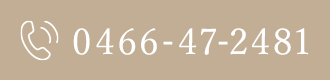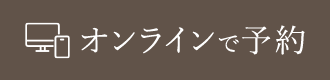自己免疫疾患とは
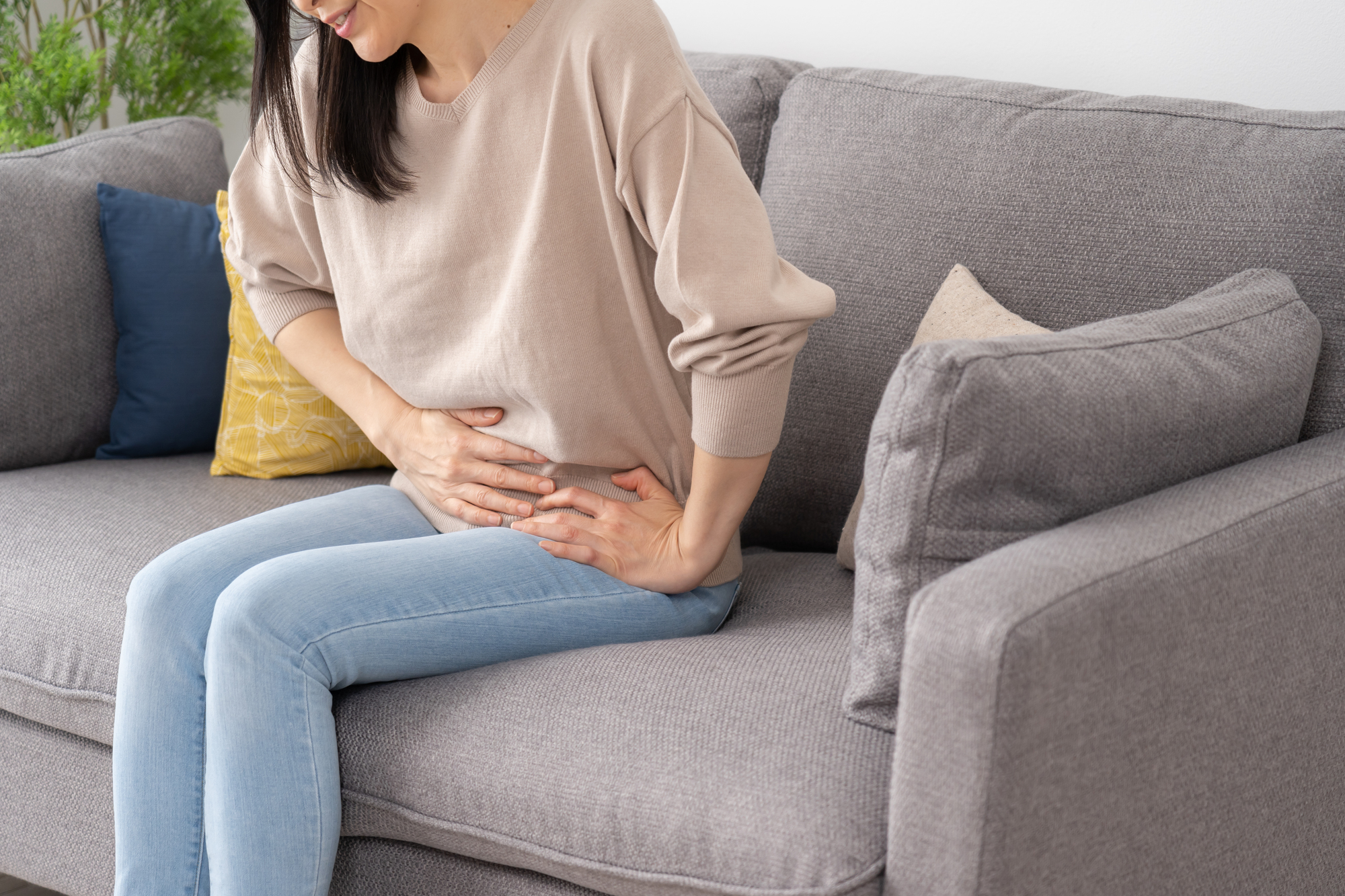
本来、免疫力や抵抗力は健康な状態であれば、体外から侵入する病原菌などの異物に対してのみ働きます。しかし、何らかの要因によってこの防御システムに異常が生じると、自分の細胞と外部の病原菌との区別ができなくなり、病原菌が存在しないにもかかわらず、自身の細胞や組織を誤って敵とみなして攻撃してしまいます。その結果、体のさまざまな部位で慢性的な炎症が生じ、さまざまな症状が現れることになります。
リウマチ・膠原病科で行われる検査・治療
血液検査
| 免疫関連 | ウマトイド因子(RF)、抗CCP抗体、MMP-3、免疫グロブリン、症状や疾患に応じた自己抗体検査 |
|---|---|
| 炎症関連 | CRP(炎症反応)、ESR(赤血球沈降速度) |
| 貧血関連 | 赤血球、Ht(ヘマトクリット)、Hb(ヘモグロビン[血色素量])、血小板 |
| 生化学検査 | 腎機能、肝機能 |
画像検査
| X線検査(レントゲン検査) | 関節や骨の状態を把握するために、基本的な画像診断を行います。 |
|---|---|
| CT/MRI検査 | 骨の異常を高感度で検出できるほか、滑膜や関節周囲の軟部組織(筋肉・靭帯・軟骨など)の炎症や腫れも確認できます。 |
リウマチ・膠原病科で使用される治療薬
- 非ステロイド抗炎症薬
- 副腎皮質ステロイド
- 抗リウマチ薬(DMARDs)
- メトトレキサート(MTX)
- 免疫調整剤
- 免疫抑制薬
- 生物学的製剤
- JAK阻害薬
膠原病内科で診察可能な疾患
- 関節リウマチ
- 全身性エステマトーデス
- 全身性強皮症
- 多発性筋炎/皮膚筋炎
- 乾癬性関節炎
- 脊椎関節炎
- 髙安動脈炎
- ANCA関連血管炎
- 変形性膝関節症
- リウマチ性多発性筋痛症
- シェーグレン症候群
- 痛風
- 混合性結合組織病
- 抗リン脂質抗体症候群
- 血管炎症候群、変形性関節症
関節リウマチ
関節リウマチは、膠原病の中でも最も患者数の多い疾患です。免疫機能の異常によって関節を覆う滑膜に炎症が生じ、それが異常に増殖することで骨や軟骨が破壊されていきます。治療をせずに放置すると、関節の変形や破壊が進み、日常生活に支障をきたす恐れがあります。
主な症状としては、関節の痛みや腫れ、朝起きたときのこわばりなどが挙げられます。とくに手や足の指、手首に症状が現れやすいですが、肘、肩、膝、足首などの関節にも見られることがあります。
さらに、全身のだるさや微熱、食欲不振といった全身症状に加えて、皮膚(皮下結節など)、眼、肺など、関節以外の部位に症状が出ることもあります。
近年では、関節リウマチの治療法が大きく進化しており、骨や軟骨の破壊を防ぐ薬に加えて、強力に炎症や破壊を抑える生物学的製剤やJAK阻害薬が使用されるようになりました。
これにより、免疫の異常をコントロールし、病気の活動をほぼ抑えた「寛解状態」を目指すことが可能となっています。
関節リウマチは、早期の診断と治療が非常に重要です。気になる症状が少しでもある場合は、できるだけ早めに医療機関を受診されることをおすすめします。
全身性エリテマトーデス
この疾患は英語で「systemic lupus erythematosus(全身性エリテマトーデス)」と呼ばれ、略して「SLE」とも言われます。SLEは、自己免疫によって全身のさまざまな臓器に炎症や損傷を引き起こす疾患で、特に関節、皮膚、腎臓、神経などに症状が現れます。
原因ははっきりしておらず、主に20~40歳代の女性に多く発症します。
主な症状には、発熱、全身の倦怠感、関節痛、皮疹、光線過敏症、脱毛、口内炎などがあり、その中でも有名なのは、蝶形紅斑と呼ばれる、両頬と鼻に現れる赤い皮膚の発疹です。
症状は人によって異なり、全く症状が現れない軽度のものから、重症の場合は腎臓に障害を引き起こす「ループス腎炎」や、神経系に関わる精神的・神経的な症状が出ることもあります。また、この病気は指定難病に指定されており、場合によっては医療助成の対象となることもあります。
全身性強皮症
強皮症は、皮膚や全身のさまざまな内臓(食道、消化管、肺、心臓など)が徐々に硬化(線維化)する病気で、また手足の先端の血流が悪くなる(末梢循環障害)という特徴があります。この疾患には「全身性強皮症」と「限局性強皮症」があり、それぞれに適した診断が必要です。
全身性強皮症では皮膚だけでなく内臓も線維化しますが、限局性強皮症は皮膚にのみ影響を及ぼし、内臓には影響しません。
また、全身性強皮症でも、進行の速さや内臓への影響の程度は患者ごとに異なります。
原因は明確には分かっていませんが、免疫系の異常、線維化、血管障害の3つの要素が重要であるとされています。
現在、根本的な治療法は確立されていませんが、症状の改善が期待できる治療法は徐々に明らかになりつつあります。
多発性筋炎/皮膚筋炎
多発性筋炎・皮膚筋炎は、筋肉や皮膚、肺などを中心に全身に炎症が起こる自己免疫性疾患です。
皮膚筋炎では、指の関節の背に盛り上がった赤い発疹(ゴットロン丘疹)、肘や膝の外側にざらついた紅斑(ゴットロン徴候)、まぶたの腫れを伴う紫紅色の発疹(ヘリオトロープ疹)など、特徴的な皮膚症状が現れます。症状は筋肉の炎症を主体としながらも、全身のだるさや関節の痛み、間質性肺炎を伴うこともあります。
ただし、すべての方に同じ症状が出るわけではなく、皮膚症状のみが見られるケースもあります。
なかでも注意が必要なのが、間質性肺炎の進行と悪性腫瘍の合併です。
治療の基本はステロイド薬の投与ですが、肺の病変が急速に進行する可能性があると判断された場合は、免疫抑制薬を早期から併用することがあります。
乾癬性関節炎
乾癬(皮膚に炎症が起こる慢性疾患)に加えて、関節の痛みやこわばり、変形などの関節症状が現れる病気で、「乾癬性関節炎」と呼ばれます。特に手足の指の関節に症状が出やすいのが特徴です。
原因ははっきりしておらず、30〜50歳代で多く見られ、男女差はほとんどありません。日本人では乾癬患者さんのおよそ10〜15%に合併するといわれています。
乾癬の皮膚症状は、髪の生え際、肘、膝、臀部などによくみられ、赤い発疹とともに、銀白色のフケのような鱗屑(りんせつ)が現れるのが特徴です。
治療は、症状の進行を抑えながら、患者さんの生活の質(QOL)を向上させることを目的に行っていきます。
脊椎関節炎
脊椎関節を中心に、胸鎖関節や仙腸関節といった体幹部の関節、さらに手指などの末梢の関節にも炎症が起こる疾患です。
慢性的な腰痛がきっかけで発見されることが多く、眼の炎症や下痢などの症状を伴うこともあります。
この病気に特徴的なのが「炎症性腰背部痛」で、安静にしていても良くならず、むしろ運動することで症状が和らぐという性質があります。加えて、手指や肩などに痛みや腫れ、こわばりが生じることもあります。発熱や全身のだるさを伴うことも少なくありません。
進行すると関節の可動域が制限され、柔軟性が失われることで「背中を反らせない」「首を左右に動かしにくい」といった症状が現れるようになります。
髙安動脈炎
髙安動脈炎は、大動脈およびその分岐にあたる太い血管に炎症が起こることで、血管が狭くなったり詰まったりする病気です。こうした血管の変化は、脳・心臓・腎臓などの重要な臓器の働きに影響を及ぼすことがあります。
また、炎症を起こす部位によって現れる症状も異なります。
原因は明らかになっていませんが、発症の大半は女性で、特に15歳〜35歳の若い世代に多く見られます。
初期には、発熱や体のだるさ、風邪のような症状から始まることがよくあります。
治療はまず、炎症をコントロールすることが基本となります。副腎皮質ステロイド薬のほか、血栓の予防薬や、必要に応じて免疫抑制剤を併用することもあります。
ANCA関連血管炎
ANCA関連血管炎は、血液中に抗好酸球細胞質抗体(ANCA)という自己抗体が現れ、さまざまな臓器の細い血管に炎症を引き起こす病気です。
この病気には、顕微鏡的多発血管炎、多発血管性肉芽腫症(以前はWegener肉芽腫症と呼ばれていたもの)、好酸球性多発血管性肉芽腫症(旧称:Churg-Strauss症候群/アレルギー性肉芽腫性血管炎)の3つの疾患が含まれます。
原因はまだはっきりしていませんが、他の膠原病と同様に自己免疫の異常が関与していると考えられています。
主な症状としては、発熱や全身のだるさ、体重減少、筋肉痛、関節痛などが挙げられます。
日本では、ANCA関連血管炎の多くのケースで肺に病変が見られるため、肺の状態を詳細に評価することが重要です。
治療は、副腎皮質ステロイド薬に加えて免疫抑制薬を併用するのが基本です。症状や検査結果の改善を確認しながら、ステロイドを徐々に減らし、免疫抑制薬中心の治療に移行していきます。
変形性膝関節症
変形性膝関節症は、加齢や長年にわたる膝への負担の蓄積が主な原因とされています。
代表的な症状は、膝の痛みや体重をかけた際の違和感・痛みです。レントゲン検査で、関節の隙間が狭くなっていたり、軟骨の下の骨が硬くなっていたり、骨の端に骨棘(こつきょく)が形成されている所見があれば、変形性膝関節症と診断されます。
ただし、膝の痛みを訴えて来院される方は多く、その背景には関節リウマチなどの膠原病や偽痛風といった炎症性疾患、細菌感染、痛風などの代謝性疾患、さらには使い過ぎ・肥満・けがによる軟骨の摩耗など、さまざまな原因が考えられます。
これらはそれぞれ治療法が異なるため、適切な鑑別と除外診断が非常に重要です。
変形性膝関節症に対する手術治療は、年齢や変形の進行具合によって方法が異なりますが、一般的には人工膝関節全置換術(TKA)が広く行われています。